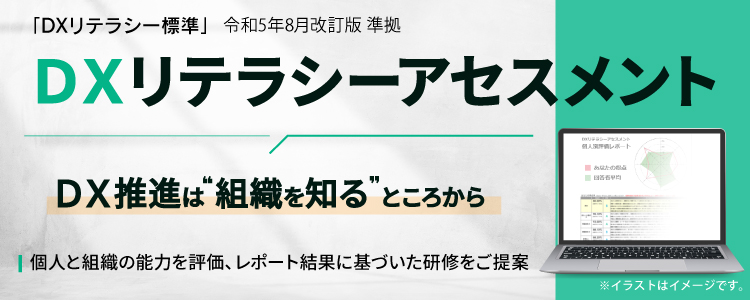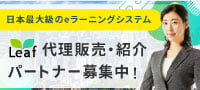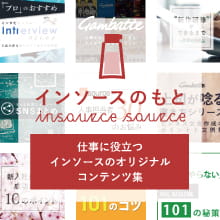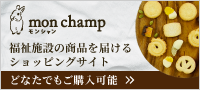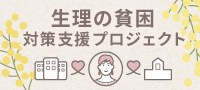【オススメ本紹介】複雑な世界を読み解く情報との向き合い方
-
ビジネススキル
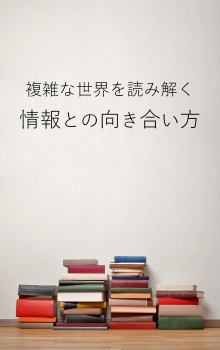
様々なマスメディアが存在し、誰もが情報発信できる今の時代において、自分に必要な情報を収集し、正確な情報か否かを見極めることは非常に困難です。 一方で、いつどこにいても大量の情報にアクセスできることはビジネスに限らず人生全般において非常に心強い味方でもあります。 情報に踊らされず、独自の情報収集と分析能力さえ身につければ、大きな武器にも成り得ます。
本書は国際情勢をメインテーマに、新聞やニュースに対して著者独自の視点で「(1)情報を知る」「(2)情報を読む」「(3)情報を使う」「(4)情報を活かす」の4ステップで情報の読み解き方を語っています。 これまで漠然とニュースや新聞を見てきた方、情報を見て意味が分かる程度で留めてしまっていた方は、本書をきっかけに情報への感度や向き合い方が変わります。 嘘の情報に惑わされず、複数の情報から全体像の把握や今後の見通しを立てる等、情報を知識に、知識を知恵に昇華し、情報を読んで使うことの面白さを感じていただければ幸いです。
書籍情報
中西輝政 著
『情報を読む技術』
(サンマーク出版、2011年)
1.主観的で書き手の結論ありきの情報に惑わされない
人は無意識のうちに、自分に都合のよい情報、自分の考えに近い情報に目が行きがちになります。 「自分は間違ってなかったんだ」と自身を肯定したいからかもしれませんが、それでは事実に基づいた情報や耳が痛い情報等の真に必要な情報を得る機会を逃してしまいます。 それは書き手も同じで、だからこそ「初めから結論ありきの情報」には特に注意が必要です。
「初めから結論ありきの情報」に惑わされないためには、以下の2つを念頭に置いておく必要があります。 一つ目は、情報は常に主観的であるということです。 一見、根拠やデータに基づいた結論に見えるかもしれませんが、そもそも提示されている根拠やデータが書き手の結論に都合の良いものを主としているかもしれませんし、 同じデータでも切り口を変えて伝えられている可能性もあります。 ただ事実を報じているだけの客観的情報に見えても、それは発する側の何らかの主観に基づいています。 「ドキュメンタリー」というと、あたかも客観的な視点が貫かれているように思われがちですが、目の前で起こっていることを克明に収めたとしても、作り手の主観を排除することはできません。 たとえば、サバンナでライオンがインパラを狩ろうとしていたとします。 そこで作り手が逃げ惑うインパラにフォーカスすれば、視聴者はインパラが逃げ切れるように願うでしょう。 しかし、そこにお腹を空かせた子ライオンの映像が差しはさまれたら、途端にインパラは大事な食糧となり、視聴者はライオンを応援するでしょう。 このように読み手の心情をどちらに持って行くかは、作り手の主観一つで左右されるということです。
二つ目は、書き手の思考過程がきちんと示されているかということです。 「この根拠があるけれど、ここに少し矛盾がある」「AとBを比べるとやはりAが正しいように思う」「この結論を否定する根拠で有力なものにCというものがある」など、 結論を支える根拠だけを提示するのではなく、対立する意見もきちんと示し、結論に至るまでの紆余曲折の思考過程が明らかであれば、信用に足る情報と言える可能性が高くなります。
2.伝えられるべきことが省かれているわかりやすい情報に踊らされるな
忙しいビジネスの現場において、わかりやすさというのは非常に重視されています。 しかし、情報を読むときには「グレーゾーン」を知るという姿勢が大切です。
世の中にはAかBかはっきりと正解があるものはほとんどなく、AともBとも言えないグレーゾーンがあります。 そうはいってもAかBを選ばなければいけなくなった時に危険なのが「分かりやすすぎる情報」だと著者は主張しています。 白黒はっきりせずにもやもやしている中でどちらかを決める時、「こういうリスクがあって、でもメリットもあってとどっちつかずな主張」と、 「平易な言葉ではっきりとした主張」があれば、おのずと後者を選ぶことが多い傾向にあります。 しかし、あらゆる条件やリスクが錯綜する中で分かりやすすぎる情報というのは、伝えられるべき重要な情報が欠けていたり、前提条件が曖昧だったりすることがあります。 イギリスやアメリカでは、親から子へ伝える処世訓といった趣の本が良く出版されます。 その中で必ずと言っていいほど言われるのが、迷っている状況に耐えられず、安易に答えを出そうとし始めたら、破滅が近づいている証拠だ」という戒めです。 分かりやすさに逃げ込むなとも言い換えることができます。
分かりやすい情報が悪というわけではないですが、焦った状況やもやもやした状況で、 安易に分かりやすさで選んでしまうと落とし穴が潜んでいる可能性があるということに、私自身十分注意をしていきたいですね。
3.圧倒的支持を受けているものは対立する視点を考えてみる
本書で紹介されているエピソードのひとつで、ユダヤ人の世界には、「全会一致は無効」というルールがあります。 圧倒的支持を受けているものは、じつは危険だという発想です。 圧倒的支持を受けているものへの「警戒心」が情報の本質を見抜く視点を養います。
政権の支持率で考えてみるとわかりやすいかもしれません。 そもそも様々な利害が複雑に絡み合っている世の中で、万人が全員手を挙げて賛成できる政策など存在しません。 逆にいえば、熱烈に支持されているものは、どこか無理をしていて、対立する利害を抑え込み、虚構を振りまくことで万人に耳当たりのいいようにしているだけになります。 それゆえ、いずれひずみが決定的になり崩壊へとつながっていきます。 さまざまな可能性がありうる中で、たった一つにすべてを賭けてしまったら、その一つがダメになった時に全滅してしまいます。 そうなる危険を知っているからこそ、ユダヤ人の世界では、異論があることをむしろ歓迎し、全会一致は無効という保険をかけているのです。
「そうは言っても全会一致になることなんてほとんどないよ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、 例えば創業社長が「これで行く」と言ったことに対して、反対意見や別の角度からの意見を言える人はどれくらいいるでしょうか。 影響度が高ければ高い人ほど、周りがイエスマンとなり、発言者の意見が全員の意見となり得ることは往々にしてあることです。
全会一致は盲目的になっている可能性が高いということを念頭に、私も多角的な視点で議論ができる理想的な組織づくり、チーム作りを目指したいと感じました。
▼関連リンク
- <表面的な知識だけではなく、複数の視点でより深堀して考えられるようになってほしい>
【公開講座】クリティカルシンキング研修~本質を見抜く力を養う - <仮説をもとに情報を集め根拠に基づいた企画・提案をできるようになってほしい>
【公開講座】情報活用力養成研修~情報の収集・整理・分析編 - <複雑な状況を整理し、第三者に分かりやすく伝えられるようになってほしい>
【公開講座】図解力向上研修~情報を整理し、分かりやすくする編 - <チーム内での議論を活性化させ、生産性の高いチーム作りをしたい>
【公開講座】(半日研修)会議デザイン研修~心理的安全性を高め、「意見が出ない」を解決する - <戦略的に物事を考え、進むべきシナリオを描けるようにしたい>
【全力解説】戦略思考研修~「意思」「直観」「論理」で目的達成のシナリオを描く - 【株式会社インソースコンサルティング】人事・組織・経営課題のソリューション提案・施策実施~定着までを一貫支援
- 【お問合せはこちら】教育体系見直しや人的資本経営推進、社内講師・専門人材養成
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
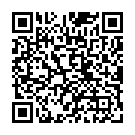
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。