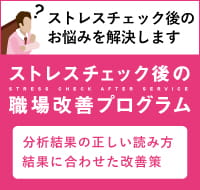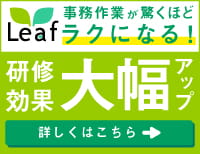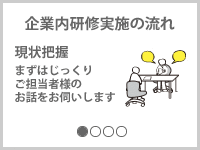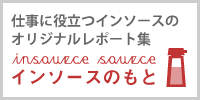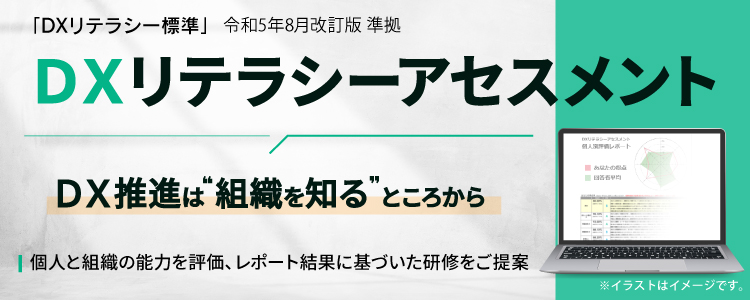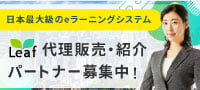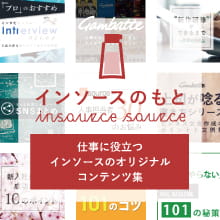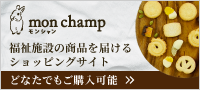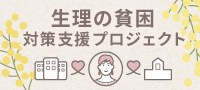新人OJTガイド

株式会社インソース著
舟橋清之監修
2008年4月5日(土)発行『月刊人事マネジメント4月号』にインソース編、弊社OJT研修担当講師の"舟橋清之"監修の「新人OJTガイド~若手を自立させる、上手な仕事の教え方~」21ページの特集記事が掲載されました(P33~54)。
 特集記事の内容
特集記事の内容
「新人OJTガイド」は、前半はOJT担当者の持つべき理念、後半はケーススタディによるエピソード形式の内容で新入社員向けのOJT研修をご紹介しております。前半部では、OJTにおける意義、OJTの果たすべき役割についてお話しいたします。後半部では、実際にOJT担当者が遭遇する数々の問題をOJT担当者からの悩み相談という形でケーススタディにして、問題とソリューションをご紹介しております。
【 理論編 】
(1)OJTを理解しよう
この章では、OJTを語る前にすべての前提となる「OJT」の理解を深めることを目的とします。OJTを行う上でベースとなる考え方は以下の4つです。
- 新人に企業、組織の理念を理解させ、「考え方の軸」を築けるよう導く
- 「考え方の軸」の明確にさせることで、判断力をもった人材に育てる
- 組織人としての考えを持たせ、自身の仕事の意味と全体の中での自分の
仕事の位置づけを理解させる - 実際の業務を通し、その人にあった指導法を見出し実践する
これらの考えを担当者が理解して臨むことで、小手先の技術で業務を覚えさせる表面的な指導から一歩踏み込んだ、骨太な人材育成が可能になります。
(2)OJTリーダーに求められるもの
OJTリーダーに求められるものとしては、以下の4つが挙げられます。
- 組織の理念・仕事の本質の理解
- 強力なリーダーシップ
- "責任は自分がとる"という覚悟
- 自己を再確認し、自分を正す
つまり、OJT担当者には組織人としての自覚と理解に裏打ちされた覚悟と責任がその根底に必要とされます。
(3)後輩・部下の現状を把握する
個別に、各人にあった指導が行えることがOJTの強みです。しかしそのOJTならではの強みを活かすには、一人一人が「何が」「どのくらい」できるのか、レベルを明確にすることが不可欠です。
(4)教える・指示を出す
育成においては、実際に業務を与える前に「なんのために、この作業を行うのか?」という意味を伝えることが重要です。
仕事の意味を理解することで、仕事内容や進め方に関する判断が自分でできるようになり、周囲に大きな迷惑をかけるリスクが減ります。
また、何を目的とした仕事であるかの理解に加え具体的な手順や期待水準を伝えることで、仕事にかける時間や労力を自身で調整することを考えるようになります。
【 ケーススタディ編 】
(5)わがままな部下の場合
仕事を選り好みしたり、反抗的な態度に出る部下に対しても頭ごなしに怒るのは適切な対応とはいえません。
不平・不満は一方的に押さえつけるのではなく、受け止めた上でこちらの意向を伝えるという「理解」のクッションを挟んだ対応をしましょう。
仕事を選り好みする部下には、その仕事を任せる意義を説くことが重要ですが、単に仕事の重要性を説明するだけでなく、それを達成することによって得られる部下自身の成長などについて言及することが効果的です。
(6)甘えている部下、自分で考えない部下を指導する場合
甘えている部下、自分で考えない部下には実は2つのタイプがあります。一つは依存心が強く、何でも「どうしたらいいんでしょう?」と指示を仰ぐタイプです。 このタイプの部下には、逆に「どうしたらいいと思う?」と問い返しましょう。
少しずつでも自分で考える習慣を身に付けさせることが大切です。もう一つのタイプは、何も報告してこないタイプです。 このタイプは一見自立していそうですが、実は「これくらいなんとかなる(なんとかしてもらえる)」と楽観視しているだけというのがほとんどです。
このタイプには、考えさせる習慣と共に定期的な報告の癖をつけましょう。どちらのタイプにも対応としてまずいのは、放置することです。 根気強く指導していきましょう。
 特集記事の内容
特集記事の内容
【 研修の特徴 】
「新人OJTガイド」でもご紹介したように、一口に「OJT」といっても様々な手法があります。また、指導者のレベルや組織の育成体制も多様です。
インソースではこのような現状に対応すべく、「OJT研修」にも「基礎編」「演習編」など、バリエーション豊かな研修ラインナップを組んでおります。
「こんなOJT研修があったらいいのに」とお悩みならば、是非一度ご検討下さい! [OJT研修トップページ 概要や実績、考え方はこちらから]
【 主な研修ラインナップ 】
- OJT研修 ~基礎編(1日間)
OJTの基本的な考え方と進め方を学ぶ、OJT入門編 - OJT研修 ~演習徹底編(2日間)
OJT の基本を習得後の、部下への接し方向上カリキュラム - OJT研修 ~フォローアップ編(2日間)
部下のモチベーション管理まで含んだ欲張りカリキュラム - OJTリーダー研修(1日間)
リーダーとして部署全体のOJTを推進するプロジェクト作成編 - 【公開講座】OJT指導者研修~新人・後輩指導の基本スキル習得編
人気のOJT研修 公開講座
※その他、「課長向けOJT研修」など、各階層向けのOJT研修もご用意しております。
 OJT活用ツール:お役立ちシート集
OJT活用ツール:お役立ちシート集
 インソースのHRMレポート
インソースのHRMレポート- 【講演録】人的資源管理の流れ
- 日本型経営を支える管理職の役割「現在求められる中間管理職の役割」
- 管理職に求められる能力について
- 「成長企業の人材育成」
- 経営マネジメントのコツ~バーチャルマネジメント研究所
 ビジネスに役立つレポート
ビジネスに役立つレポート- ビジネス文書文例集
- あなたにも簡単にできるクレーム対応の勘所
- オフィス節電プロジェクト
- インソースが考える「奥の手・猫の手」
- インソースマナーブック
- 社長に必要なノウハウを学ぶ2ヶ月間
 インソース研修の特徴
インソース研修の特徴- 研修の考え方
- 研修の流れ~事前課題
- 研修の効果測定
- 研修呼び覚まシステム
- 受講者の声
- 講師の特徴
- Q&A
 インソース研修一覧
インソース研修一覧- テーマ別研修
- 階層別研修
- 年代別研修
- 業界業種別研修
- 官公庁・自治体向け研修
- 部門別研修
- AI・RPA研修
- 新作研修
- 1名から参加できる公開講座
 研修カレンダー
研修カレンダー