インドネシア共和国に子会社を有している法人のご担当者様、インドネシア共和国への進出をご検討されている法人のご担当者様、インドネシア共和国の知識を深めたい全ての方、法務部門、海外事業部門、コンプライアンス部門、経営企画部門等のご担当者、または上記テーマにご関心のある方
トップページ > 公開講座 > 公開講座 テーマ別研修ラインナップ 人事/総務/財務/法務研修 > インドネシア事業運営の最新実務ポイント ~ジャカルタ駐在経験を持つ弁護士が、データ保護規制、贈収賄、労働法など詳細に解説~
インドネシア事業運営の最新実務ポイント ~ジャカルタ駐在経験を持つ弁護士が、データ保護規制、贈収賄、労働法など詳細に解説~

No. 99K242102
受講対象target
講義のねらいoutline
インドネシア共和国は世界4位の人口数(約2憶7380万人)を誇る東南アジアの発展途上国であり、平均年齢は29歳と若い(中国は38歳)。また、ミャンマーやタイ等と異なり、歴史上、国軍のクーデターが成功したことはなく、政治的に安定もしている。
歴史的にも日本人として唯一外国元首の妻となったデヴィ・スカルノの存在や、バブル期前からの日系企業の進出により日本人が多く駐在していることから、親日家の多い国としても知られる。
2020年には、外資規制を原則として撤廃する通称「オムニバス法」が制定され、従前の外資規制に基づき必要であった現地パートナーとの提携関係の解消が原則として可能となったため、現地子会社の運営に関する経営判断の選択肢が増えた。
Covid-19の影響が薄れ、日系企業の投資熱も2023年夏頃から戻りつつある中、2023年及び2024年の法改正等、インドネシアにおける最新の法務留意点を総括する。
主催団体organizer
本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。
研修プログラム例program
1.インドネシアの法令と司法制度の特徴
2.インドネシアにおける子会社の機関設計
・会社形態ごとの具体例の解説
・最低資本金、最低投資額、外資規制等の概要
3.インドネシア子会社のコンプライアンス(贈収賄に関する法規制)
・贈収賄に関する法規制と事例
4.インドネシア現地法人が留意すべき契約実務
・言語法、損害賠償、準拠法、紛争解決、債権回収など
5.インドネシア子会社において生じやすい不祥事の類型
6.インドネシア労働法の基礎
・日本企業が押さえておきたい基本的なポイント
7.インドネシアにおける模倣品対策の法制度と実務
・商標制度の基礎と模倣品が発見された場合の対策
8.その他最新実務ポイント
・初の包括的規制として2022年に制定された個人情報保護法の概要
・言語法に関する最高裁判所通達2023年第3号
・憲法裁判所による改正オムニバス法の一部(労働法関連)の違憲無効判断
注意事項notice
◇◇◇法改正等によりプログラムは変更となる場合があります。◇◇◇
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。
【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
◆受講形式のご案内
【オンライン受講の方】
オンラインには、開催形式が<zoom開催>と<LIVE配信開催>の2つがございます。
開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。
ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。
<zoom開催> 講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ
<LIVE配信開催> ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55
※LIVE配信は、企業研究会様の協力会社である、株式会社ファシオ様のイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用されております。
お客様の会社のネットワークセキュリティによってはご視聴ができない場合もございますので必ず【動作確認】をしていただいた後に、お申込ください。
※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
【会場受講の方】
お申込時に、会場情報(住所・アクセス方法)をご確認ください。
筆記用具はご自身でご準備ください。
お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください
スケジュール・お申込み
(オンライン/セミナールーム開催)schedule・application
オンライン開催
講師instructor
渥美坂井法律事務所・外国共同事業 パートナー弁護士 柿原達哉 氏


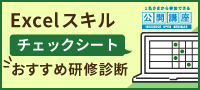


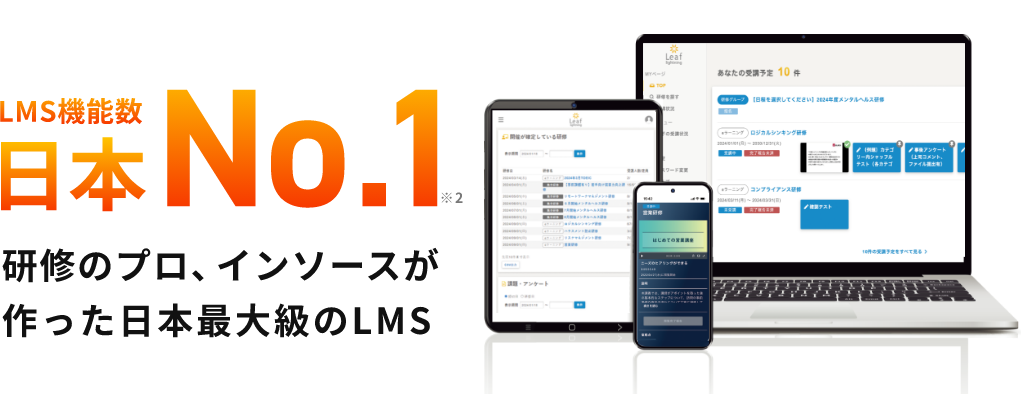



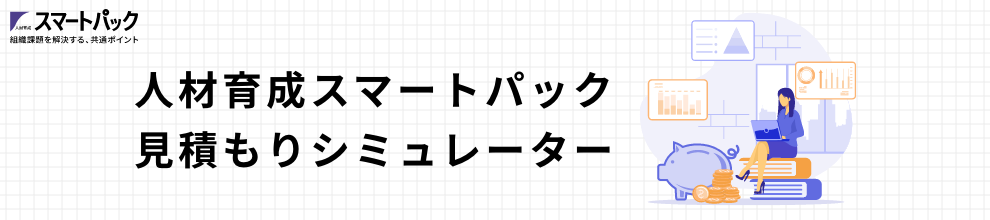
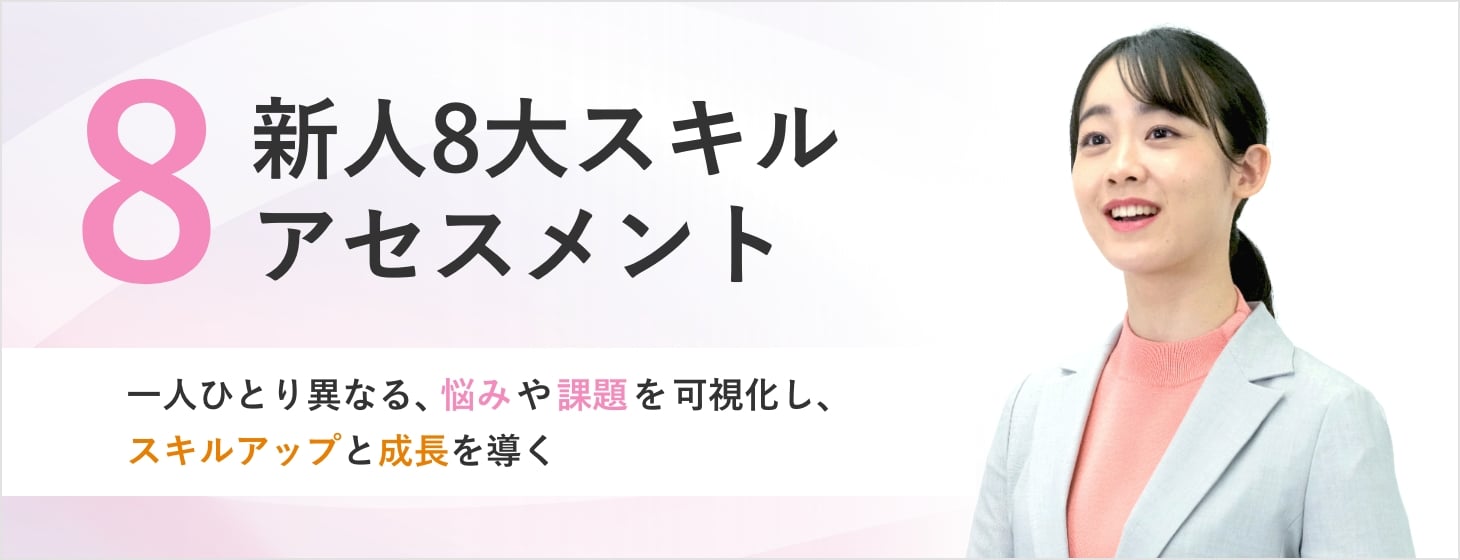





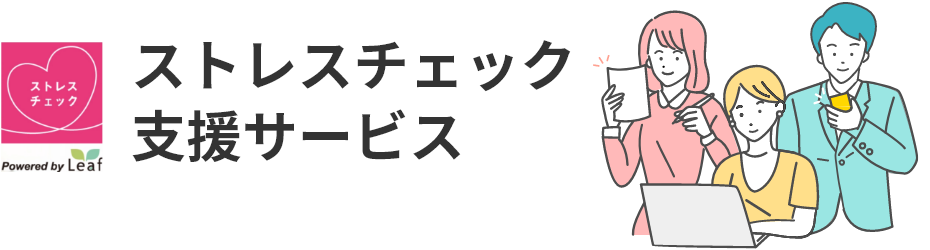




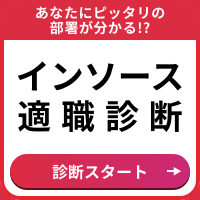
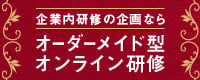
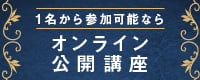


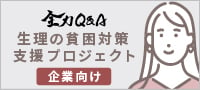




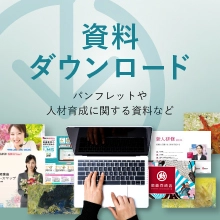
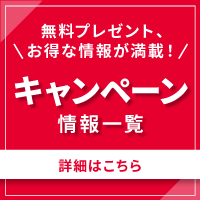
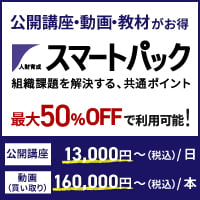
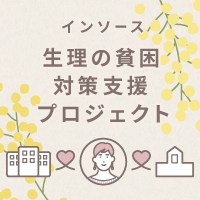








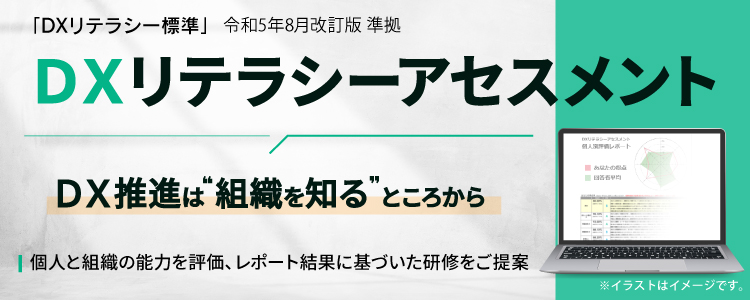


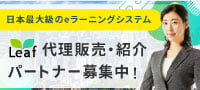




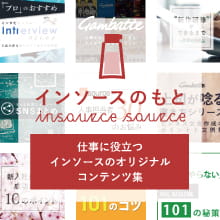
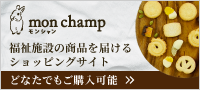
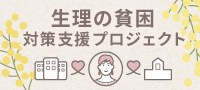




実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!