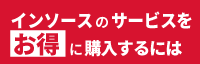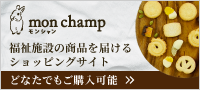1.はじめに ~
選手と同じ視界ゼロの環境を活用した体験型研修「OFF T!ME Biz」
視界ゼロの環境「ブラインドサッカー」とは?
ブラインドサッカーは、アイマスクを装着した4人のフィールドプレーヤーと、アイマスクの装着が不要なゴールキーパー(晴眼者または弱視者)を1チームとして競技する5人制サッカーです。
フィールドプレーヤーは、鈴の入ったボールの音と周囲からの掛け声や音などを頼りにボールを取り合い、ゴールを奪い合います。
ピッチサイズは、フットサルと同程度の40m×20mで、サイドラインには腰上くらいまでの高さの壁があり、サイドからピッチ外にボールは出ません。そのサイドの壁の外から、監督がチームに指示を出します。
相手ゴール裏にいる「ガイド」というメンバーが、相手と味方の位置関係やゴールまでの距離、ゴールの枠(左右ポスト)の場所などを、声や音でフィールドプレーヤーに伝えます。
目が見える人と見えない人が協力し、試合を進めます。


※北日本・東日本・中日本・西日本
ブラインドサッカー男子日本代表チームは、2024年のパリ・パラリンピックに参加し、出場した世界の全8か国の一角として健闘しました。(2024月以降、世界ランキング3位)
なお、女子日本代表チームは、世界ランキング1位を維持しています。
日本ブラインドサッカー協会とインソースとの連携
特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会(以下「JBFA」)は、『ブラインドサッカーを通じて、視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること』をビジョンに掲げ、ブラインドサッカー、および、ロービジョンフットサルの強化・普及を推進するほか、ダイバーシティ啓発活動などの普及活動を行っています。
インソースは、JBFAのパートナー企業(※)として、JBFAの様々な活動や取組みを支援しています。
※スポ育パートナー、サプライサービスパートナー(外部サイト)
視界ゼロの環境を活用した体験型コミュニケーション研修「OFF T!ME Biz」と
ブラインドサッカーとの繋がり、および、研修の特徴
この研修で目指していることは、ブラインドサッカー自体を体験することではなく、ブラインドサッカーの選手達と同じ視覚環境下で、どのようなコミュニケーションをとれば相手が理解でき、適切に伝わるかという点です。
■中身は、サッカー(競技)ではなく「研修」
・主に、コミュニケーション主体のワークを行います。
※体験から気づきを得ていただきくことがメインとなるプログラムです
・スポーツが苦手か得意かは関係なく、どなたでも気軽に研修を受講できます。
・チーム対抗で身体を動かして考える体験を、多く組み入れています。
・ブラインドサッカーの競技で使うアイマスクや音が出る専用のボールを使用します。
※スポーツ競技(=ゲーム)としてのサッカーを一切行いません
■体験で学ぶ中で、怪我に繋がる危険性なし
・動きやすい服装が理想ですが、日常業務で着用しているスーツのままでも受講できます。
※日常の延長での動きやコミュニケーションで構成される研修です
・アイマスクを装着して視界を遮った状態で動くときは、ゆっくりと場内を歩きます。
※場内では、走りません
※相手との激しい接触は一切なく、怪我の心配もありません
2.研修開発の経緯
「知る」「理解する」から、「OFF T!ME Biz」を
通じて『気づく』と『再発見する』へ
元々JBFAでは、障がい者スポーツに対する認知や理解を広めることを目的として、視覚健常者(目の見える人:晴眼者)に向けてブラインドサッカーの選手と同じ体験をできるプログラムを実施してきました。
実施する中で、「障がい者スポーツを知る・体験する」ことを越えて、その体験から「気づく」「再発見する」ことが多いことが、受講者の声から分かってきました。
そこで、JBFAでは、「障がい者スポーツを知る機会」でなく「障がい者スポーツを通じた学びの機会」に繋がるよう、プログラムを改善・パッケージ化し、研修に進化させました。
「見えない」状態だからこそ気づける、
チームワーク発揮に必要な要素
コミュニケーションや、信頼関係、チームとしての親密感、明確な役割分担、目標設定など、「チームワーク」に必要な要素は、日常で当たり前のように「大切」とされています。
しかし、あまりに当たり前すぎて、その大切さに気づきにくくなっているのではないでしょうか。
この研修では、受講者を「目が見えない」という日常とは異なる環境に置き、他者の助けが必要な状況をつくります。
そこから、「チームワークで状況を乗り越えること」の大切さや、そのために必要な様々な要素を、改めて認識できます。
例えば、「コミュニケーション? 私は大丈夫!」...っと思い込んでいた方が、なかなかチームメイトとコミュニケーションできず孤立する姿も、この体験型研修を通じて可視化されます。



体感して得られた気づきは、ダイバーシティ(多様性)への適応力にも繋がる
この研修を通じて得られる気づきは、ダイバーシティへの適応力にも繋がります。
「それぞれが個性を発揮し互いに個性を認め合い生かし合うことで、チームとしての成果を上げる」
という、まさに、現代社会で求められるスキル・マインドを生みだすきっかけとなるのです。
3.研修のねらい
視界ゼロの環境を活用した体験型コミュニケーション研修「OFF T!ME Biz」から得られるチームビルディングと、多様性への適応力
「OFF T!ME Biz」では、受講者同士が、視界ゼロの環境の中でコミュニケーションを通じたチームビルディング(output)をはかっていきます。
その結果、多様性に対する適応力(outcome)が高まると考えています。
コミュニケーションと、下図にある黄色い丸の7つの要素は、チームビルディングに必要で大切な因子です。
これら7つの要素に関する気づきが得られるよう、視界ゼロの環境でワークを行っていきます。
※こちらの図は横にスクロールしてご覧いただけます

4.こんな場合におすすめ
-
組織内では、一体感が乏しい。
チームで仕事をしていることの大切さを考えたい。
見えない状態でのチームワーク体験のため、お互いの存在価値を身体で実感できる。
-
一連の研修では座学が多く、受講者の集中力欠如が課題。座学だけではなく、体験型を取り入れたい。

オフサイト研修や合宿型など、詰まった研修スケジュールの合間に、短時間で効果的に実施できる。
-
管理職や経営者などの上層部が一般的なコミュニケーション研修に飽きてしまい、主旨を訴求しにくい。

体験型、かつ、視覚訴求型、しかも、「初めての体験」のため、訴求しやすい。
-
本格的なチームビルディング研修は屋外での実施が多く、その場所までの移動に時間がかかり屋外の研修に参加しにくい。

大きめの会議室や都市圏の小規模の体育施設でも実施でき、場所を選びやすい。日本全国で実施できるため、職場や近隣でも開催できる。
-
ダイバーシティを推進中だが、そもそも「ダイバーシティ」がなぜ大切か、組織内に訴求できていない。

体験が、ダイバーシティのことを自分事として捉える機会になり、本質を学びやすい。
-
障がい者の採用を進めているが、障がい者社員と他の社員の間にある「見えない壁」をなんとかしたい。障がい者雇用を組織力に変えたい。

実際に身をもって障がいを体験し、当事者として受講できる。
障がい者の個性も学び、組織の
中で業務に活かしやすい。
5.プログラム内容、準備、体験
(例)「OFF T!ME Biz」、120分で構成する場合
※こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます

要件定義(事前のお打ち合わせ段階で)
お打合せでは、お客さま、JBFA講師、およびインソース担当との三者間で「要件定義」を設定します。この「要件定義」とは、お客さまの背景をもとに、どのような意図や思いでワークを企画し、受講者に何を伝えていきたいのか等、研修ご担当者様のねらいを言語化することです。
要件定義を元に、研修ご担当者様が思い描いた「ねらい」に落とし込める振り返りワークや、講師によるファシリテーション等を開催前に計画し、当日に実現させます。
事前準備(開催場所の設定と、個人の持ち物)
▼場所の確保と広さの事前確認(広さの目安と、形状)
・屋外でも実施できますが、風雨の影響があるため、屋内をお勧めします。
・6~8名を1チームとして、1チームに必要な広さは、5.5m×5.5m=30.25m2
(≒ 約30m2)が、最小限の広さの目安です。
・最小限で2チーム以上で構成し、実施します。
・開催1回で受講する人数(チーム数)により、必要な広さが変わります。
・受講者全員を複数チームに分け、安全に全員が同時に動ける広さが最低限必要です。
・会議室等を使うことも可能ですが、室内の机や椅子、教卓、備品等をすべて
壁側に寄せたり室外に出すことで床に何もない箇所が、広さの基準です。
(例)計2チーム(12名~)で約60㎡以上、計3チーム(18名~)で約90㎡以上
・小規模の体育館等にある他の球技のコートから、広さの目安をご確認ください。
(例1)バレーボールのコートの場合、1面が18m×9m=162m2のため、
コート1面で、計5チーム程度(1回で約30~40名)までの広さを確保できます
(例2)バスケットボールのコートの場合、1面が28m×15m=420m2のため、
コート1面で、計14チーム程度(1回で約80~100名)までの広さを確保できます
・歪な形ではなく広さに余裕がある会場なら、実施できます。ご不安な場合はご相談ください。
※会場の画像(各方向)を事前に提出いただき、JBFAで実施可否を確認することがあります
・極端に形が整っていない部屋や、長方形でも過度に細長い場所は、使用不可です。
<理由>
- 講師から離れたチームは講師の声を聞き取りにくく、講師の動作が見えないため
・床が平面の場所を、ご手配ください。
※階段があるホール等では、実施ができません
・候補会場での実施可否を確認するため、会場の写真の共有をお願いする場合があります。
・候補会場の写真等で実施可否が不明な場合、会場を下見する場合があります。
▼個人の準備物
・運動しやすい服装、底が滑りにくい靴の着用
・汗拭き用のタオルや、着替え
・水分補給のための飲み物(水筒、ペットボトル等)
・身体を動かして体調を崩すことがご心配な方は、念のため、健康保険証をご持参ください。
※体験の中で身体を動かすことが多いですが、激しい運動ではありません
※健康保険証をご持参される場合は、貴重品のため自己管理をお願いいたします
あなたも体験してみませんか?
不定期開催で、インソースの無料セミナー(インソース主催)がございます。
無料体験ワークショップの詳細はこちら!
開催日程のリクエストも、お待ちしています。
無料セミナー以外では、JBFA主催による体験ワークショップを随時開催しています。
※有料での参加
<2025年 関東地区での体験ワークショップ「OFF T!ME(オフタイム)」>
東京都内で、平日の夕方以降に短時間で開催します。
▼開催日時と場所 (90分間を予定)
★5月16日(金) 19:00-20:30 高田馬場会場
【満席】5月28日(水) 19:00-20:30 神田会場 ※5月14日現在で満席
◎6月 9日(月) 19:00-20:30 神田会場
★6月25日(水) 19:00-20:30 高田馬場会場
◎7月 7日(月) 19:00-20:30 神田会場
★7月25日(金) 19:00-20:30 高田馬場会場
・残席が僅かとなっている日程もございます。
・残席状況が都度変わるため、インソースの営業担当にお問い合わせください。
・上記の日程以降も、開催が決まり次第、順次掲載します。
・どの会場も、各路線の駅から徒歩圏内です。
※会場等の詳細は、開催前日までに申込者に直接お伝えします
・終了後、希望者のみで懇親会(別料金)を行うことがあります。(任意参加)
・高田馬場会場(★)にご参加の方は、室内履きの運動用シューズをご持参ください。
・神田会場(◎)では、室内履き不要です。土足のままで受講できます。
▼参加費 ¥4,000/人(税込)
・当日、会場で参加費を直接お支払いください。
※領収書の発行(後日お渡し)が可能です
▼お申込方法、その他
・インソースの営業担当にご一報、または、インソースのお問合せフォームをご利用ください。
・申込締切は各開催日の3営業日前ですが、それ以降のご希望は、個別にご相談ください。
・ご参加可能な人数は、原則、1組織あたり2名様までとさせていただきます。
・会場のご案内や当日の開催可否、その他の留意事項(JBFAの規約等)については、お申込者に事前にお伝えします。
6.受講者の声
新入社員向け研修を受講されたお客さまから
- 相手が理解しているかどうかを気にしながらコミュニケーションをとろうと思う。
- 実際にやってみることで、いかに自分基準で話しているか分かった。連絡する際などに、相手の立場を考えて話していきたい。
- 相手の立場になって考えることと、自分の案をがんがん出すことを今後業務に活かしていく。
- やる前はできるかとても不安でしたが、やってみたらとても楽しかったです。障がいを持っていてもスポーツだったり生活だったり、工夫ややる気、努力次第でのりこえられることが多くあると実感しました。


新人研修以外で受講されたお客さまから
- ワークの難度が少しずつ上がっていく中で、チームワークもどんどん良くなっていくのを感じられた。ワークの合間で講師の方のアドバイスを聞くと、次で実践できて、皆で成長を感じることができた。
- 声を出してお互いに共有できることがとてもうれしかったので、これからも続けていきます。
- 楽しさが強いチーム作りに大事、との言葉がとても印象に残りました。