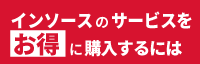学生生活最後の夏休みに、インターンシップや内定者アルバイトなどを体験して、ビジネスの厳しさを垣間見る人たちもいるだろう。
50年も前、私の大学時代の夏休み。何かアルバイトしようかな...と思っていたら、知人の紹介で小さな広告コピーを頼まれた。一度OKをもらうと取引先が次の取引先を紹介してくれ、少しずつアルバイトが仕事に変化していった。
仕事を始めて2年ほど経っただろうか、「仕事」に対する意識が一変したことがあった。某大手保険会社の季刊会報誌の制作メンバーだった時の話。
年4回季節ごとに発行し顧客に配られる会報誌は、生活提案情報が大半を占める読み物的な色合いが濃かった。中でも特に大事な巻頭特集は、制作会社の社長同席で案出し~構成を決めるミーティングが毎回開かれた。その年のテーマは「パーティ」だった。まだパーティが身近ではなかった時代、もっと気軽に小パーティを!とのコンセプトで、「どこでどんなパーティを」の案出しが重要だった。
夏号のミーティングの2週間ほど前、社長からこんなことを言われた。
「僕は口を挟まないから、ディレクションをとってみなさい。今回は君が親方だ。ライターの仕事だけでなく、ページ制作全体を把握することは今後の君の仕事に必要なことだから」
私はそれまで、人のリードに任せて記事を書き、意見を言うだけだった。自分自身の仕事としての真剣みに欠けていたことを突き付けられて、巻頭を任された嬉しさより、緊張で気が重かった。
ミーティングはデザイナー、カメラマンなどを加え6~7人、みんな私より年長だった。「これで私は、今後使えるかどうかを評価されてしまうんだ」という重圧で、頭も気持ちも固まってミーティングは弾まない。昨日まで考えてまとめていた自案なんか飛び去って、何も残っていない。みんなの意見をまとめることも、面白いヒントも出せず、進行もおぼつかなかった。一座の沈黙に声も膝もガクガク震えて、「もうだめだ」という絶望が先に立ち、情けなさに涙がこぼれそうだった。
デザイナーの一人が筆記具を静かにしまい始めた。「待って!帰らないで」と気持ちの中で叫んでいたが声にならなかった。「今日は進まないようなので、私はこれで」と言われた。ほかの人達もそろそろと帰り支度を始めた。
「物干し台パーティ、というのはいかがでしょうか」
突然、自分のものとも思えない私の声が話し出した。すると、昨日までに作った私案がスラスラ出てきた。物干し台(屋根の上に洗濯物を干すためだけに置かれていたスノコ状の床)で夕涼みがてら、小さな集まりを楽しもうと話した。
「おもしろいね~」みんなが座り直して、耳を傾けメモをとり始めた。急に活気が出てきて、それぞれがさまざまな意見を言い始めた。もう私が多くを話さなくても、どんどん打ち合わせが進んだ。
私は、浮かれた学生アルバイトとプロとのギャップに打ちのめされていた。
いくら一生懸命でも、それだけじゃダメ。きちんと人に伝えて形にして、はじめて仕事だと認識した。メンバーが席を立って帰ろうとしたのは、私への非難ではない。また、帰らずに座り直したのは、私への優しさからではない。どちらも、彼ら自身が「良い仕事をしたい」からであったと理解できた。プロの厳しさ・恐さ・強さを垣間見て、目を覚ました。「これから頑張ります」と言うのも空しく、口に出せなかった。
「このままではいけない、このままでは私は何者にもならずに消えてしまう」
本を読んで、人に訊いて、四六時中考えて、セミナーに行って、経験を増やして、我武者羅に勉強した。その後、半世紀を一応プロとして暮らしてきたが、一度も「Best」の仕事はない。ただ、あの日の立ち往生をきっかけに自分はプロになった、とはっきり言える。
たった半日の出来事だったが、私には終生忘れられない経験になった。
2019年 7月 10日 (水) 銀子