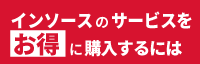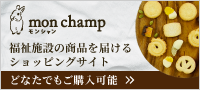![]()

≪第4回≫「『技術(知識)伝承』における現状と課題」~「人的資源管理の現状と新しい流れ」
≪第4回≫「『技術(知識)伝承』における現状と課題」~「人的資源管理の現状と新しい流れ」
1/28(東京)、2/7(大阪)で『インソース新春セミナー』題して開催いたしました神戸大学経営学部経営学研究科 上林憲雄教授の講演「人的資源管理の現状と新しい流れ」をお届けいたします。
┏―――――――――――――――――――――――┓
【上林憲雄 教授】
英国ウォーリック大学経営大学院ドクタープログラム修了後、
2005年神戸大学大学院経営学研究科教授、経営学博士。
専攻は人的資源管理、経営組織。
┗―――――――――――――――――――――――┛
◆技能の明確化について◆
一方、「(1)作業現場レベル」での話では、働き方、ということがホット・トピックスの一つになっています。
先ほど、「日本的経営」はもはや死語のようになったとお話ししましたが、それは、長らく、男性の正社員をベースにした経営のシステムであったからです。
それも、企業の忠誠心が非常に高い同一企業でずっと勤続し続けるような正社員を理想とした経営システムでした。
しかし、そのような画一的な雇用形態のみでは、世の中の変化には対応できません。
そこでパートさんとか、アルバイト社員とか、契約社員、派遣社員といった新しい勤労者の人たちが、会社で働くようになってきましたが、そういう方々の働き方、あるいはモチベーションどのようにあげるかいうことが非常に重要な、「人的資源管理」(HRM)のトピックスになっているんですね。
それに関連することですが、これまで安心、安全な職場環境と言われていたような現場や、長らく無事故だったような工場でも、最近思いもかけないような事故が起こるようになったという話を、現場の人からよくうかがいます。
その大きな原因となっているのが「技術(知識)伝承」です。これがうまく行われていないのが、現場でおこる事故の原因の一つではないかと考えています。
この「技術(知識)伝承」の問題は、最近の「人的資源管理」(HRM)の中で議論されていることです。
実はこれには、正解はありません。ですから私がこれからお話しすることは、あくまで私が勝手に考えたことというレベルにとどまりますが、組織における3階層、それぞれのレベルにおいて、この「技術(知識)伝承」の問題を考えたいと思います。
+++
まず、「(1)作業現場レベル」の話をします。もう過ぎてしまいましたが、団塊の世代が一気に退職することになって、その技能が下に伝わらなくなるという「2007年問題」がありました。
しかし、これはいうまでもなく、2007年だけの問題ではありません。この「技術(知識)伝承」をどうするかについて、以前、経営者協会や組合、連合さんなどと一緒に調査をさせていただいたことがあります。
そのときに現場・作業レベルにおける「技術(知識)伝承」の問題として挙がった論点は3つです。
まず、「技能の明確化ができるかどうか」という問題です。私が調査した際には、製造業、非製造業すべてに、ノウハウという意味も含めて技能の伝承に関するヒアリングをさせていただきました。
やはり、現場レベルでは、「自分たちの持っている強み」を良く理解していないなど、「技能」というものが目に見える形で明確になっていないことが多かったです。
よく「技能」は「暗黙知」だということをいいますが、この「技能」を明確化できるかどうかということが、「技術(知識)伝承」における論点として非常に重要です。
では、技能を明確化するにはどうしたら良いのでしょうか?技能を持っている方に、「技能マップ」を作ってもらったり、「研修を開催」してもらったりというのも方法の一つですね。
+++
最近では、ちゃんと若い人たちに技能を伝えることができる方に報酬を支払うというような、インセンティブ(報酬)の仕組みまで作っている会社さんも結構あるようです。
あと、どこの企業さんでも、現場の工場に行くと「技能マップ」が張ってありますが、これについても非常に面白いことがわかってきました。
この「技能マップ」は、いわゆる技能の「見える化」に当たりますが、技能伝承がうまく言っている企業さんは、実は、「技能マップ」の横軸、つまり技能の仕分けに非常に成功しています。
技能伝承では、個々の作業の間の関係、つなぎ、全体の中での位置づけができるかどうかが一番重要となってきます。うまくいっている会社さんの場合は、この横軸の、技能の分け方というのがユニークな場合が多いです。
◆技能の「継承機会」について◆
また、技能や知識の「継承機会」をどうするかというところも論点となっています。
私は、当然、企業側はちゃんとした「継承機会」を設けていると思っていたのですが、調査をしてわかったことは、特別な機会などは設けず、OJTのような形で「技術(知識)伝承」をおこなっていることがほとんどでした。
これは悪いことではなく、日本的経営の強みでもあるのですが、ただ裏返して言うと、OJTだけやっていますというのは、「技術(知識)伝承」を体系立てて実施したり、計画立てて研修の機会を設けたりすることを行っていないことの裏返しでもあります。
「継承機会」を今後は増やしていきたいとおっしゃっていた会社さんは多かったですが、実施できない最大の理由は、そんな時間はないということでした。
+++
それから継承者と被継承者の話に移りますが、継承する人は大体50代くらい。被継承者は大体20代後半から30代です。問題は、その間の40代の方は「技術(知識)伝承」をあまりやっていないということです。
また、「技能の明確化ができない」ということがそもそもの問題点だったわけですが、私が調査をさせていただいてわかった面白い点は、継承者と非継承者の間の心理的なコミュニケーションにギャップがあるということです。
先輩から技能を学びたいという気持ちや、後輩に技能を教えたいという気持ちは両社にあるのですが、うまくコミュニケーションができないという悩みを抱えておられることが非常に多かったです。
アカデミックとはとてもいいがたいですが、「最近の若い人というのは飲みに誘ってもぜんぜん来てくれない」という話も良く聞きます。40代後半から50代の方はかつては日本的経営の得意技である「飲みニュケーション」を行い、そこで大事な話をしていたわけですが、だんだんそういう"お家芸"が通じなくなっているようです。
+++
そのほか、アンケートと同時に、「技術(知識)伝承」について、いくつかの会社にインタビュー調査させていただいたんですが、一つ面白いなと思ったのは、技術に任せられるところは思い切って技術に任せてしまうということです。
これは技能継承において重要なところです。当たり前といえば、当たり前ですが、意外と盲点になっています。
「人間じゃないとできない」部分、それは各社違うと思いますが、伝承のための労力は、やはり「人間じゃないとできない」部分に絞ったほうがいいと思います。つまり、何から何まで、すべての技能を伝承しなければならないという考えに陥る必要は必ずしもないということです。

 『内気でも活躍できる営業の基本
『内気でも活躍できる営業の基本
研修会社インソース新卒3年目・中島が伝える営業の頑張り方』
「きみは営業に向いてない」
周りの人にさんざん言われていながら入社早々営業担当になってしまった中島が伝える、営業の頑張り方