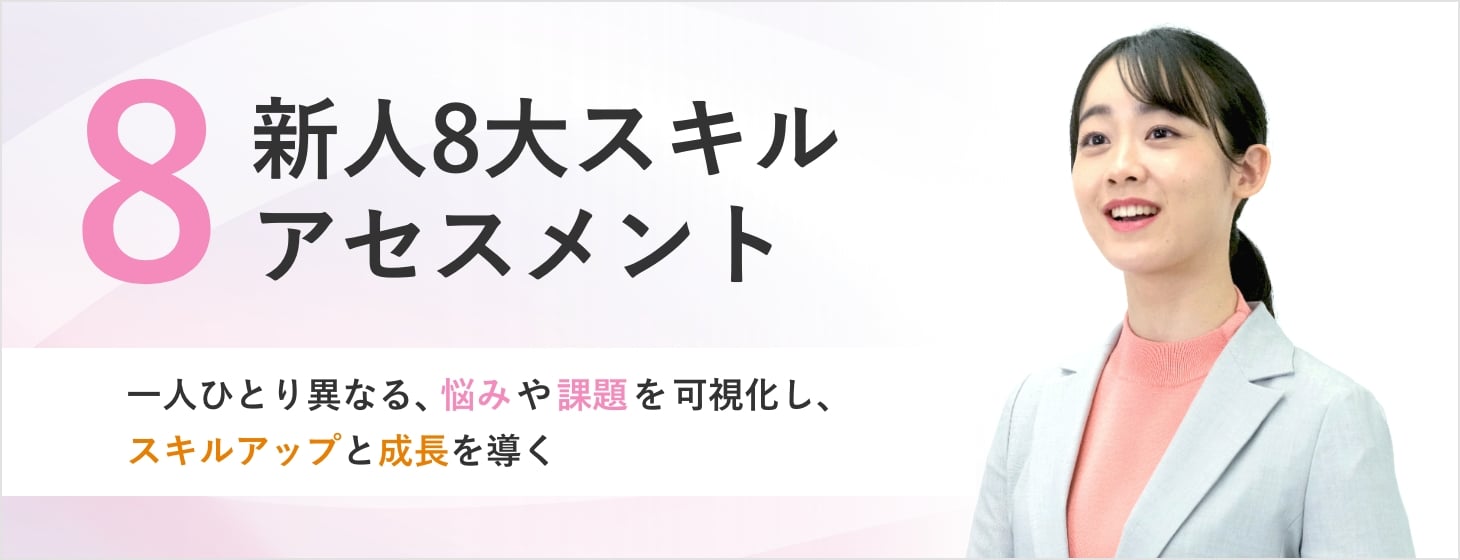マナーだけで終わらせない!4月中旬以降の新人教育

年間9万人以上の新入社員教育を実施している「研修のプロ」が、最新の新人研修のポイントについてお伝えします。
今回は、新入社員の早期戦力化のために必要な新人教育とオススメの研修とともにご紹介します。
2025年のテーマは「今の新人への寄り添い」と「組織への定着」
「指示通りに行うのは得意」「主体的な工夫は少ない」「自身の権利を主張したがる」といった声を、今の新人の特徴として多くの組織からききます。
一方で、離職を恐れて新人への指導がしにくくなってきているという声も、年々強くなる傾向にあります。「真面目」で「言われたことはしっかり行える」という特徴を生かし、必要なことは最初に教育しておくというのが現在の新人教育に必要な点です。
また、離職を防ぐには新人に自社で働くメリットを感じてもらう必要があります。そのためには、新人研修を充実させることも施策の一つです。入社時研修のラインナップを増やすことはもちろん、入社直後だけでなく半年・1年後のフォロー研修を充実させる組織も増えています。
新人研修のご担当者さまのお悩み
多様化する新人教育において、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
<お悩み例>
- 入社から配属まで少し余裕があるが、どんな教育をしたらいいか考える時間がない
- 予定変更で研修期間中に1日空きができてしまったので、何か研修を企画したい
- 毎年同じ研修内容を実施しているが、時代に即した内容を取り入れたい
そこで今回ご紹介するのは、4月の「中旬以降」にオススメの新人教育です。
新人研修を「マナーだけ」では済ませたくない研修担当の方は、ぜひご検討ください。
マナーだけじゃない、4月中旬以降にオススメの新人教育
モラル&コンプライアンス研修~不祥事・情報漏えいと組織への損害
社会で働くためにはルールを守るだけでなく、モラルの意識が必要です。モラルとは何なのか、自分の行動によってどんな影響があり、何がコンプライアンス違反につながるのかを身近な事例から学んでいきます。
できるビジネスパーソンの10の心得・行動~職場の常識編
信頼を与えるあいさつや言葉づかい、身だしなみなど基本的なマナーのステップアップした内容、会社の備品の扱い方、清掃の仕方、コスト意識など職場で働く際に必要な知識で、ここまで配慮できたら「できる」と感じるという点を取り扱います。
テキストコミュニケーション研修
若手社員などから聞かれた実務で困った点を多く盛り込み、指示の受け方、ホウ・レン・ソウの仕方、社外とのメールのやりとりのポイントをおさえます。
DX入門研修~実践を通してデジタルへの向き合い方を身につける
ChatGPTを用いて、文章要約やプログラミングを体感することで、新入社員の情報感度を高め、業務効率化のマインドを獲得します。今後社内で活躍できる人材になるために、DXを理解し、デジタル技術を活用できるマインドを獲得していただきます。
金融リテラシー向上研修~お金の基礎知識を習得する
「金融リテラシー」とは、お金に関する知識や判断力のことで、経済的に自立した社会人になるために必要不可欠です。いまや、金融の仕組みや経済動向等を理解することは、現代人の必須の能力であるといえます。
仕事の進め方研修~ビジネスゲームで学ぶチームワークとコミュニケーション
仕事は一人で完結するものではなく、チームワークとコミュニケーションを意識しながら仕事を進めなければ個人としても組織としても成果が出ないことを、ドミノを使用し学びます。
シミュレーション研修~実践形式で行う新人研修総まとめ編(2日間)
「ビジネスマナー」「電話応対」「コミュニケーション(報連相)」「チームワーク」「プレゼンテーション」等のスキルを『分かる』から『出来る』ようにトレーニングし、現場で実際に実践できるようにします。
セットでおすすめの研修・サービス
新人8大スキルアセスメント~新人に求められる8大スキルを分析・可視化するサービス
本アセスメントサービスは、新人が潜在的に持っている"課題"を、この8つのスキルに分けて評価するサービスです。入社時や配属後、2年目を迎える手前などに受検をすることで、自己学習や個別指導、研修企画に活用できます。
新入社員向け!動画教材セレクション~新人8大スキルを高めるeラーニング
新入社員に身につけて欲しいスキルに沿った動画を新人8大スキルアセスメントをもとにご紹介いたします。動画百貨店ではビジネスマナーの基本からPCスキル向上まで、「即戦力になる新人を目指す」ために必要な動画・eラーニング教材を多く揃えています。
Z世代の育て方研修~新しい価値観に向き合う人材育成のあり方
本研修ではZ世代と言われる今の若手が育ってきた時代背景を振り返り、若手の価値観を知ることで、彼らとどのように関わっていくべきかを考え、個性に向き合う育成のポイントと指導者の在り方をつかみます。