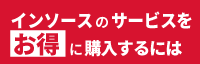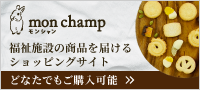「ダイバーシティ」は万能薬か?
![]()

「ダイバーシティ」は万能薬か?
- 目次
本日はバーチャルマネジメント研究所のコンテンツより、以前より経営キーワードとなっている用語の1つ、「ダイバーシティ・マネジメント」について語ります。
改めて「ダイバーシティ」とは
ダイバーシティとは多様性を表す英語で、日本企業にとっては、これまで日本的経営を支えてきたという暗黙の了解があった「長期間働き続ける、会社忠誠心を持った男性社員」という一律の勤労者観を否定し、「多様性」を経営へ導入することを意味します。
特に、グローバル化を旗印に国際的に活躍している日本企業や、男女共同参画社会の理念のもと、雇用平等や女性管理職比率の向上などといった性別の多様性の文脈で語られることが多い用語です。
時流が理由で「ダイバーシティ」を導入していないか
わたし自身も、学生向けに執筆したテキストブックの中で、「多様化する働く人たち(女性労働、高齢者雇用)」、「多様化する雇用形態(非正規雇用)」、「多様化する労働時間と場所(裁量労働・在宅勤務)」、「多様化する働くことの意味づけ(ワーク・ライフ・バランス)」という章を設け、日本的経営の"ダイバーシティ"化について詳しく説明しています。(ご関心がおありの向きは、『経験から学ぶ人的資源管理』有斐閣、2010年、第13~15章をご参照頂けると幸いです。)
しかし、そもそもなぜ、昨今になってことさらダイバーシティの導入が叫ばれるようになってきたか、何ゆえにダイバーシティ・マネジメントが企業経営の論理と結びつくのかについては、世間ではあまり議論されることはありません。
「社会の時流がそのようだし、ダイバーシティは逆らいにくい理念だから我が社でも導入してみよう」という、よくわからないまま導入しようとされている人事担当の方々も多いかも知れません。
不安定な経営環境下ではシステムの多様性が必須
ずばり、ダイバーシティが企業経営の論理と結びつく理由は、企業が環境との相互作用の中で経営しており、その経営環境が時代を経るごとに不安定になってきている、という事実と関係します。企業にとって、不確実性が増し、どのように経営していかないといけないか先が読みにくい時代になってきたのです。
システム論の考え方を援用すると、一般に「システム」は、その周囲の環境とうまく相互作用を行い、こうした環境との適合性が高い場合に、1つのシステムとして長期にわたり存立することになります。
システムに多様性がある場合、たとえシステムの環境が不安定化し、めまぐるしく変わったとしても、システム内の多様な要素を組み換え、変わった環境に適応できるような構造に再編させることにより、環境に適応することが可能です。
逆にいうと、システムに多様性がない(すなわち、システムを構成する要素がそもそも少ないか、あるいは要素間の関係性がある特定のパターンにしか組み得ない)場合には、環境の変化に対しては弱く、環境が変わればシステムとして適応ができなくなってしまうことになります。
日本の経営環境は不安定になった
ここから、日本企業が、かつては多様性を内包させたシステムではなかったにもかかわらず、比較的長期にわたり業績や収益を上げ続けることが可能であった1つの理由として、経営環境の不確実性が、かつては現在に比べると遙かに小さく、長期にわたって、どういった事態になるかが予測可能な状況が続いてきたためではないか、と推論することができます。
実際、1960年代以降、高度経済成長期から低成長の時代へと経済的・社会的環境は変わったように見えますが、企業経営にとっては、そのシステムの根幹を覆すほどの大変化ではなかったのです。
ただ、それが1990年代のバブル崩壊や平成不況の長期化、技術革新(IT革命、ナノテク等の新技術の発達)、リーマンショック、コロナショックなど、環境変化の程度が従前と比べると遙かに大きくなっており、したがってシステムに多様性をビルトインさせておく方が、経営的に有利となってきた、という状況があるのです。
現象が起こる理由を考えるスタンスこそ重要!
以上、多少理屈っぽかったかも知れません。やや飛躍しますが、私がここで言いたかったことは、何でも時流の現象やキャッチフレーズを鵜呑みにしてしまわない、という姿勢こそが肝要ということです。まずは疑ってみることです。
疑うというのは、何でもかんでも相手を批判し、責め立てることを意味しません。それは、冷静に覚めた眼で、周りに流されることなく自分なりに考えてみることを意味します。
例えば、上記のようにダイバーシティが求められている理由を考えることができれば、この声高に叫ばれているキャッチフレーズの背景や意味を冷徹に分析することが可能になります。
いわば、ダイバーシティが決して「絶対」の処方箋ではなく、特殊な条件の下で経営にとっては有効であることも理解できます。
こうしたスタンスを身につけ、物事の分析眼を身につけることは、自社のオリジナリティを高め、ひいては他社には模倣できない真の競争力をつけることにも繋がっていくはずです。