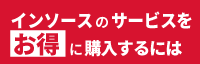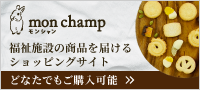【事例研究】プロシューマー戦略
![]()

【事例研究】プロシューマー戦略
- 目次
今回の語り手
インソース EA(エグゼクティブ・アドバイザー) 大島浩之
1981年 株式会社三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)入行。
主に商品企画・事務企画に従事。
02年 UFJ銀行の合併作業に携わる。
04年 取締役顧問に就任。
三和銀行においてシステム商品の9割に関与し、
20年近くに及ぶ経験をもつ。
三和銀行インターネットバンキング・HP企画の責任者。
Gomez(ゴメス株式会社)の評価(Webサイトの世界的評価機関)
2回連続第1位。
マニュアル企画・作成にも携わり、
作成マニュアルの厚さは自分の身長を越す。
トラブル対応関係にも強みを発揮。
20年 インソース EA(エグゼクティブ・アドバイザー)に就任。
プロシューマーとは
最近の商品戦略として、特にインターネット上では、プロシューマーの視点にたったマーケティングがごく普通になってきています。プロシューマーとは、Consumer(消費者)とProducer(生産者)を組み合わせた造語で、消費者が生産に加わることをいいます。これは、未来学者のアルビン・トフラーが著書「第三の波」で用いました。
現代のように成熟した高度消費社会においては、大量生産された既存の製品に満足せず、自分の求めるものを自分の手で作り出そうとする、生産と消費が一体化した新しいタイプの生活者が現れてきました。そのため多くの企業では、商品開発において、従来の「押しつけ」的なものから、生活者を意識したものへとシフトしたマーケティングの手法を採用するようになってきたのです。
インターネットバンキングとプロシューマーの視点
意外に世の中で知られていないことですが"頭の固い"銀行でさえプロシューマーによるマーケティングを採用せざるを得ませんでした。
例えば、インターネットバンキングは、独自のソフトで提供するのでなく、お客さまが一般的に使用しているGoogle Chromeなどのブラウザ上でサービスできることが不可欠です。
今から見ると不思議に思うかもしれませんが、インターネットバンキングは、最初はどこの銀行も、企業のパソコンバンキング(=ファームバンキング)の延長線上で独自のソフトウェアを提供して開始しました。ところが、企業のパソコンバンキングと違って、個人では、月数回程度の操作しかしないため、本当の意味で顧客志向にたったカンタンな操作でないと顧客の支持を得ることは困難でした。 そこで、セキュリティに配慮しながらブラウザ上のサービスを提供する方向への転換を迫られたのです。
顧客志向の業務改善
この顧客志向のインターネットバンキングにより、顧客の支持を得た銀行では、さらに、プロシューマーの視点に立ったマーケティングにより、サービスを改善しました。それは、お客さまのお問合せなどにおけるニーズを徹底的に洗い出し、お客さまの望むサービスや操作に改善するというものです。いわば「サービスを決めるのは、銀行ではなくお客さまだ」を実践したわけです。
例えば、アクセスした後の最初の画面は残高一覧にしました。論理的(システム的)には、残高照会や振込など画面には、サービスメニューの選択から入るのが、従来の"常識"でした。しかし、お客さまは、システムの整合性や美しさよりも、まず最初に、残高確認。しかも、自分の持っている預金などの残高一覧が見たかったのです。
これは、従来のように、企業自身の思惑やライバル会社の動きよりも、お客さまのニーズを優先せざるを得ないという、価値観の転換が引き起こされた一例です。こうした現象がいたるところで引き起こされているのが現代の風潮だといえるでしょう。