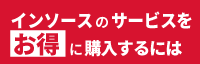「成長企業の人材育成」

 成長企業における評価制度・賃金制度について
成長企業における評価制度・賃金制度について
-評価と賃金の決め方-
いまだに“世界に冠たる『日本的経営』”という意識が残滓として企業で働く人びとの中に残っているのではないでしょうか。
20年前までの「終身雇用、年功序列、企業内組合」=“三種の神器”で総称されてきた『日本的経営』の意識要素は、実は日本社会をも規定してしまっていたと思います。
その結果、各企業の「評価制度」や「賃金制度」も企業規模の大小に関わりなく“高度成長”という「パイの拡大」が前提となりました。ある意味で牧歌的であったのかもしれません。
今日、企業が等しく成長できるという社会全体の「パイの拡大」はあり得ません。しかし“業績概念”を曖昧にしたままで、“業績”との連動性を重視しない「評価制度」や「賃金制度」の名残が随所に存在しているのも現実です。
■評価の基本は基準を明確にし、「年功」意識を払拭すること
企業が成長していくためにも、あくまで適正な評価実践を行っていかなければ、人材の流出は否めません。「評価制度」の大前提は、“何”を評価するかであり、その「評価」すべき対象を明確にする必要があります。さもなければ「評価」は恣意的なものとなってしまうものです。
「年功」による「評価」が主流の時代には、「社員の業務遂行能力は歳を経るごとに経験が積まれていくものである」という暗黙の了解がありました。その前提に基づいて処遇や報酬が決められてきたため、「評価誤差」が生まれる温床ともなっていました。
「評価誤差」とは、「ハロー効果」「寛大化傾向」「中心化傾向」による評価者によるバラつきです。
「ハロー効果」とは、ひとつ良いことがあるとそのことに引っ張られ、全てがよく見える傾向です。これでは全体的印象で判断することになり、部分的特性や能力を正しく判断できません。「寛大化傾向」とは、評価する側の性格、自信の欠如や観察不足、抽象的な評価基準等により評価に対して甘さが生じることです。
「中心化傾向」とは、例えば5段階評価などで常に「3」をつけてしまうなどのように評価対象者に対して「普通」という評価をし過ぎる傾向です。
「評価誤差」は評価基準の曖昧さと評価者自身の「評価」への無関心によって生じるものです。従って、企業は社員に何を求め、何を期待し、それに応えている判断基準を明確にする必要があります。この「基準」が曖昧であるならば、どのような評価システムを導入したとしても、結果的には評価者による「情意」が横行することになります。
以下に掲げるのは、極めて単純ですが「評価の基準」となるべき観点です。
[評価の3つの基準]
- 能力:業務を円滑に遂行する上で、必要で有用な知識や技術が蓄積されているか。また、その習得に向けての態度姿勢が明確になっているか。
- 実績:評価対象となる期間内に具体的に「何をやってきたか」という業務遂行の実績。
- 成果:業務遂行の実績を踏まえた上で、期間内にどのようなアウトプットを行ったかという結果。
■賃金制度の基本は「ペイ・フォー・パフォーマンス」
賃金とは年齢や勤続年数、あるいは将来的な「期待値としての能力」に対して支払われるものではないはずです。あくまでも「業績に連動するものである」という意識を徹底化していくことが重要であると思います。一昔前までは金融機関から「賞与資金を借りる」などという企業が散見されました。こうした企業は決して成長が望めないと思います。
さらに家族構成などの個別的な属人性要素の加味は、制度を複雑化させると同時に恣意性の温床となります。従って、賃金は個人の「仕事の内容と結果」に対して支払うものであるという点を明確にする必要があります。
当然「仕事の内容」には難易度が存在します。そこで、同じ難易度で同じ仕事内容を行う社員は、同一の報酬でなければならないはずです。
また、会社として賃金制度の機能を明確にしておくことも必要です。
以下に「賃金制度が担うべき機能」を整理してみました。
[賃金制度が担うべき機能]
- 社員を組織に引きつけ、定着させる機能。
- 社員に対して組織が価値を認める者、認めない者をメッセージとして伝達する機能。
- 社員が組織の成果に貢献するような行動をとるための動機づけを行う機能。
- 社員の個人的、社会的な欲求を満たす機能。
企業が成長していくためには、そこに働く人びとに対して年齢に関わりなく、あくまでも個々の業務遂行における「能力」、それによって生み出される「実績」と「成果」を明確な評価基準とすることです。もちろん会社として適時・適確なフィードバックを展開し、「評価」に見合った「インセンティブ」や「ベネフィット」を含む賃金制度を社員に提示していくのが重要であると考えます。
 「成長企業の人材育成」一覧
「成長企業の人材育成」一覧
- 1.成長企業における人材採用のポイント
- 2.成長企業の管理職の役割
- 3.成長企業における評価制度・賃金制度について
-評価と賃金の決め方- - 4.成長企業における労務管理について
-今なぜ、成長企業の管理職に労務管理が求められるのか- - 5.成長企業における労務管理について
-労働時間管理を通した職場マネジメントのポイント- - 6.成長企業におけるパワハラ・セクハラ防止
-ハラスメント対策は企業の内部統制課題という視点が必要- - 7.成長企業における労務管理
-自己管理を徹底させ残業時間の削減をはかる- - 8.成長企業におけるコンプライアンス遵守について
-陥りやすいコンプライアンス違反と予防策- - 9.成長企業における新人の育成について
-新人を傍観者意識にさせてはならない- - 10.成長企業における部下指導・OJTについて
-PDCAサイクルの観点で実施する部下の指導・育成- - 11.成長企業における再雇用者の活用について
-再雇用者の活用は本人と後進のモチベーションが鍵となる- - 12.成長企業における中堅社員の役割について
-企業組織の期待を敏感に受け止め、応えてもらう- - 13.成長企業における社員のリーダーシップ
-真摯な行動が周囲に影響力を行使する「リーダーシップの発揮」に繋がる- - 14.成長企業における社員の組織依存の防ぎ方
-組織における個人の役割と責任の明確化を怠ってはならない- - 15.成長企業における人材の定着化(離職率を低下させる)の工夫
-人材の定着化を自社の組織開発の活動としてとらえることが先決- - 16.成長企業における若手・中堅社員育成の必要性
-一律主義から一人ひとりの自覚の度合いや自助努力を前提にした育成- - 17.成長企業における社内制度整備
-業績評価制度を例にした社内制度のあり方- - 18.成長企業におけるリスクマネジメントについて(個人情報保護)
-最大の防御は普段からの徹底した社員の意識向上- - 19.成長企業のグローバル人材育成について
-外に向かってのグローバル化にだけ目を奪われてはならない- - 20.成長企業における組織改革について
-組織改革が進まない理由と人の果たす役割- - 21.成長企業における女性活用
-性別に関わりなく仕事が“できる”か“できない”かを問う- - 22.成長企業における障がい者の活躍推進
-「法定雇用率達成」が目的であってはミスマッチの結果で終わる- - 23.成長企業におけるメンタルヘルス
-人間関係が濃くなり、逃げ場がない状態からの脱却- - 24.成長企業における管理職の未成熟化防止
-“面従腹背”と“馬耳東風”の悪癖を防ぐ自助努力の涵養-
◆本間 次郎◆
株式会社ノイエ・ファーネ 代表取締役
1954年生まれ。大学在学中より出版・編集業務に携わり、主に労働経済関係をフィールドとし取材・執筆、編集業務に携わる。1992年から中小企業経営 者向け経営専門誌の編集および、教育・研修ツール(冊子媒体、ビデオテープ)等の作成、人材の教育・育成に関する各種オープンセミナー・インハウスセミ ナー企画の立案・実施、人材開発事業・人事コンサルティング業務に従事。
2010年11月に『人と企業組織が互いに「広い視野」「柔軟な思考」「健全な判断」に基づいて行動し、最適な働きの場を創り出していく協働に貢献する』を使命とする株式会社ノイエ・ファーネを設立。