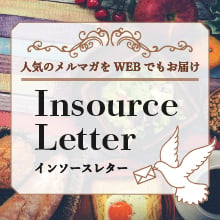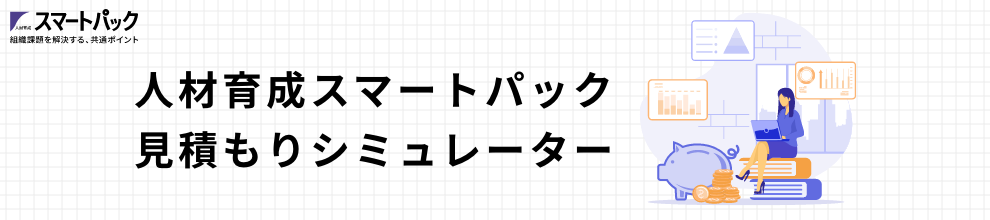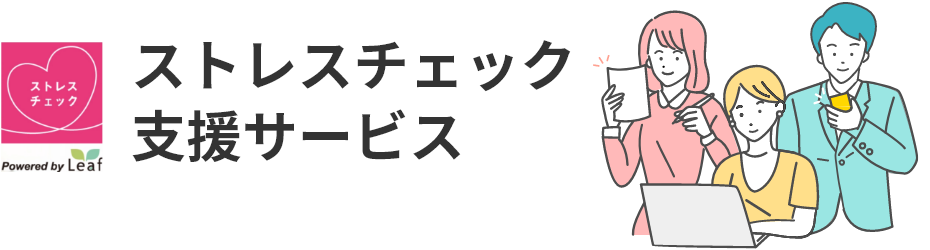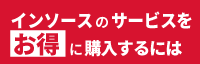2022年1月17日
2021年 コロナ下で起きた人事の重要な出来事まとめ
昨年に引き続き今年も新型コロナウイルスに翻弄された。コロナ下で起きた人事の重要な出来事を振り返る。(文・溝上憲文編集委員)
新型コロナ感染拡大が女性の雇用・賃金を直撃し、深刻な「女性不況」に
70歳までの就業機会の確保する改正高年齢者雇用安定法が4月に施行されたが、努力義務ということもあり、手つかずの企業も多かった。
またコロナの感染拡大は非正規労働者、とりわけ女性の雇用・賃金を直撃した。
2019年の労働者数は6004万人(総務省「労働力調査」)。うち非正規労働者2166万人のうち女性は1475万人と68%を占める。
とくにコロナの影響を受けた飲食・宿泊・旅行・アパレルなどの業界は非正規のパート・アルバイトが多く、女性の比率が高い。
卸売り・小売業全体の女性非正規率は35%、344万人、宿泊・飲食業は54%、196万人を占めている。
女性が多く働いている対面型のサービス業が大きな打撃を受けたが、これは世界共通の現象であり、"She-cession"(女性不況)と呼ばれた。
野村総合研究所が2021年2月に実施した調査(約6万5000人)によると、コロナ前と比べてシフトが減少しているパート・アルバイトは女性が29.0%、男性が33.9%に達した。
そのうち5割以上減少している人の割合は女性が45.2%、男性が48.5%と約半数を占める。会社の都合による休業はもちろん、シフト時間が減少しても休業手当を受け取ることができる。
コロナでシフト減の女性75%、男性79%が休業手当を受け取らずセーフティネットに課題
ところがシフト減のパート・アルバイトのうち休業手当を受け取っていない人は女性の74.7%、男性の79.0%と大半の人が受け取っていないことが判明した。
野村総研が「シフトが5割以上減少」かつ「休業手当を受け取っていない」人を「実質的失業者」と定義。
総務省の「労働力調査」を用いた全国の女性の「実質的失業者」は女性103.1万人、男性43.4万人と推計している。
2008年のリーマンショック時に非正規社員の脆弱なセーフティネットが露呈され、政府は賃金保障などの雇用安定策を講じてきたはずだった。
しかし、一連の政策でも救えない事態が今回のコロナ禍で発生し、休業手当支給の法的整備などのセーフティネットのあり方に大きな疑問符を突きつけた。
テレワークが首都圏で急速に拡大 都市と地方、大企業と中小企業で普及に格差
2020年の緊急事態宣言の発令以降急速に広まったテレワークであるが、1年以上を経て、地域・企業間の利用率の二極化の様相が明らかになった。
日本テレワーク協会の担当者は「テレワーク人口は2020年4月に東京都は67.3%、全国平均は27.9%だったが、11月に東京は50%程度に下がったものの、地方では10~5%未満のところも多い。
都市部と地方、大企業と中小企業でテレワーク利用の二極化が進んでいる」と指摘する。
テレワークで自由度の高い働き方を推進するUSEN-NEXT
東京商工会議所の「中小企業のテレワーク実施状況調査」(2021年5月下旬調査)によると、東京23区の企業の実施率は38.4%。
従業員301人以上は64.5%と高いが、50人以下は29.8%と規模間格差が生じている。
一方、大企業ではテレワークを前提とした働き方が定着している。
例えば通信業のUSEN-NEXT HOLDINGSは2018年6月からオフィスのフリーアドレス化やコアタイムのないフレックスタイムと利用制限のないテレワークを使って時間と場所にとらわれない自由度の高い働き方を推進。
2020年11月には週3日以上在宅で業務を行う社員を「完全リモートワーカー」に認定する制度をスタートし、3割近い社員が認定を受けている。
リモートワークで採用活動がオンライン化 テレワーク普及が人材獲得で有利に働くことも
また、リモートワークの利便性を高めるために同社の町田、渋谷、横浜の拠点をリノベーションしてサテライトオフィスに転換するなど完全にリモートワークシフトに移行。
採用活動でも2021年入社の社員から最終面接までオールオンラインで選考し、2022年度もオンラインでの採用活動を実施した。
同社の人事担当者は「今後テレワークが中途人材の獲得する上でも有利になる。求職者は金銭報酬の高さよりも、テレワークを含めて自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる企業を求める傾向が強くなっている。逆に言えば、そうした働き方が難しい企業は人材競争力を失ってしまうのではないか」と指摘する。
大手企業はIT投資を増やし、単なるテレワークだけではなく、ICTツールやデジタルデバイスを使いこなすことによって業務の効率化も同時に推進している。
テレワーク可能な企業とそうでない企業との間で人材競争力だけではなく、ビジネス上の競争力でも大きな格差が発生する可能性もあるかもしれない。
テレワークと並んでジョブ型人事制度の導入企業が増加
テレワークと並んでコロナ下でいわゆるジョブ型人事制度(職務等級制度)を導入する企業も増えた。
パーソル総合研究所の調査(2020年12月25日-21年1月5日)によると、ジョブ型人事制度をすでに導入している企業は18.0%、導入を検討している(導入予定含む)企業は39.6%に上る。
とくに企業規模が大きいほど導入検討企業が多く、従業員1000人以上では40%を超えた。
欧米のジョブ型雇用とまったく異なる日本企業のジョブ型雇用
欧米のジョブ型雇用は、入社時のジョブディスクリプション(職務記述書)に定めた職務や労働条件などの契約で決まり、日本のように会社命令による人事異動もなく、異動させる場合は本人の同意が必要だ。
採用においても新卒・中途に限らず、必要な職務スキルを持つ人をその都度採用する「欠員補充方式」が一般的だ。
しかし、ジョブ型と称される日本企業が導入している人事制度は1990年代後半に導入された職務等級制度と何ら変わらない。
しかも職務記述書が詳細に定義している企業も少ない。
新卒一括採用による内部育成も実施され、会社主導の人事異動や転勤も行われている。
ジョブ型導入企業の狙いは、年功にとらわれない処遇の実現
ではなぜ職務等級制度を導入するのか。
コロナ下で従来の職能資格等級に代えて日本の管理職層に職務等級制度を導入し、非管理職層にも導入準備を進めている大手精密機器メーカーの人事担当者は、目的は年功にとらわれない処遇の実現だと語る。
「何が一番フェアな制度かを考えると、国籍、年齢、勤続年数や中途入社に関係なく、ポジションの責任を担える適所適材を実現するには職能資格制度では限界がある。つまり能力は年数とともに積み上がって陳腐化しないという前提に立つ職能資格制度では、年齢に関係なく職責を担える人をふさわしいポジションに配置し、フェアに処遇していくのは難しい」
長年の慣行で組織に染みついた年齢基準を払拭できるか真価が問われる
もちろん人事制度を変えたからといって年齢に関係のない処遇が実現できるわけではない。
最大の課題は長年の慣行で組織に染みついた年齢基準の払拭だ。
人事担当者は「等級につけるときに、今何歳か、という議論を排除することが先決だ。当社でも年齢を目安に昇格させる風土があり、『彼は今何歳だから昇格には早い』といった運用が普通に残っていた。当社だけではなく、新卒入社何年目かということを大事にしている会社も少なくない。そうした年齢に関する考え方をなくしていくことが運用上の課題であると認識している」と語る。
人事制度を変更しても簡単に風土や社員の意識が変わるものではない。
自社が目指している経営理念、企業文化、顧客価値の提供などの方向性に見合った制度を設計すること、その上で試行錯誤を繰り返しながら運用を含めて地道に改善していくことが大事になる。
2022年はまさにその真価が問われることになる。
配信元:日本人材ニュース
関連サービス
- ▼ウィズコロナ・アフターコロナ時代の研修ラインナップ
~新たな戦略・決断・リスクマネジメントで組織を強化するために - ▼【公開講座】業績向上のための組織づくり研修~OODAループで目的を達成する編
- ▼女性活躍推進研修ラインナップ
~管理職、女性メンバー、ワーキングマザー向けなど、幅広く研修をご用意しております - ▼テレワーク(リモートワーク)導入研修・サービスラインナップ
~組織に適したテレワークの導入から運用までを、効果的に進めるなら - ▼マネジメント研修~ジョブ型雇用を見据えた体制作り(1日間)
- ▼オンラインセミナー支援サービス
~セミナー運営代行・オペレーター派遣・機材レンタルなど、運営を全面的にサポートいたします
最新ニュース
人事のお役立ちコンテンツ
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
人事のお役立ちニュース