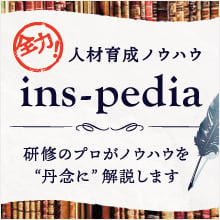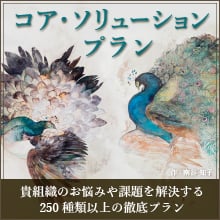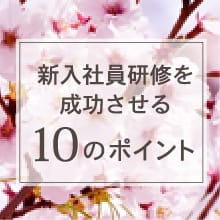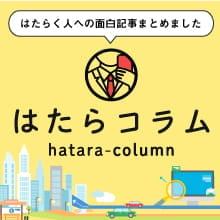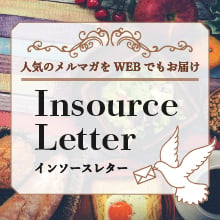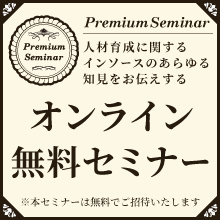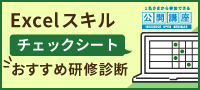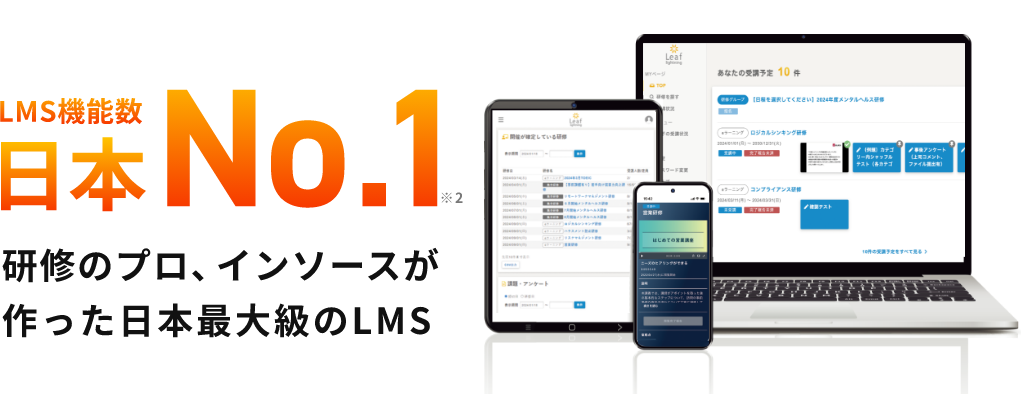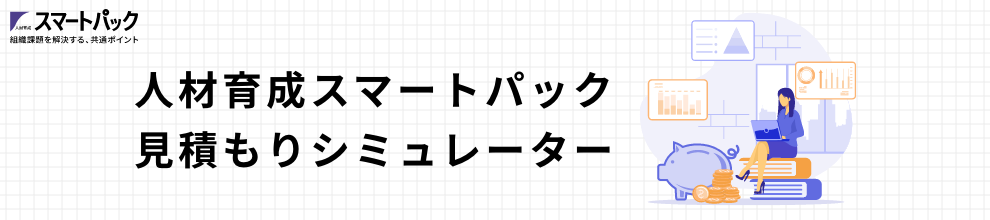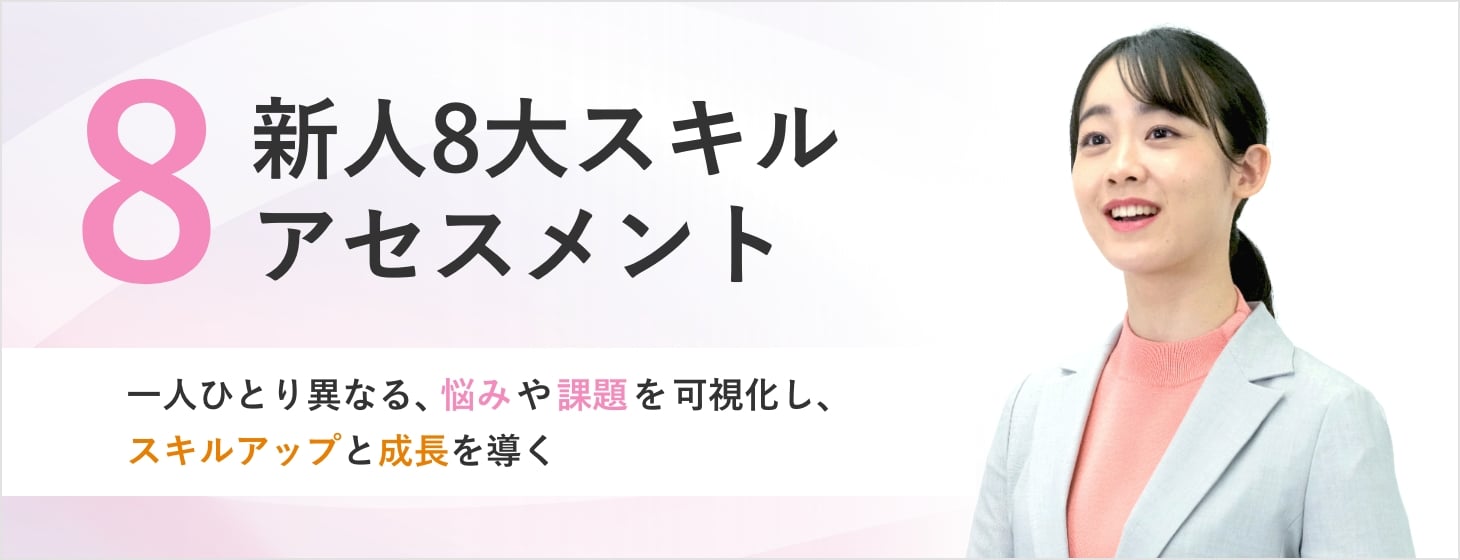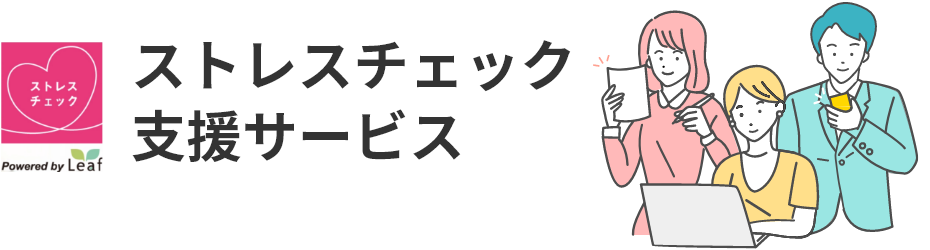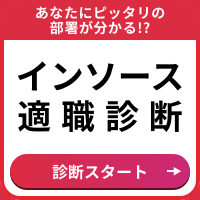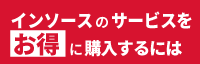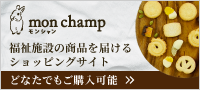2025年2月19日
令和6年版厚生労働白書、仕事や職業生活に関して強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は82.2%
令和6年版厚生労働白書によれば、仕事が原因の精神障害による労災申請件数は10年前の1257件と比べて約2倍の2683件となり、保険給付の決定は710件で過去最多となった。
年代別の仕事上のストレス内容
20歳未満から40歳代までは「仕事の失敗、責任の発生等」が最も高く、次いで「仕事の量」となっている。一方、50歳代は「仕事の量」が最も高く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」となっている。60歳以上はストレスと感じる事柄を選択しない人が最も多かったが、ストレスがある人では、「仕事の質」が最も高く、次いで「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」となっている。
就業形態別の仕事上のストレス内容
正社員は「仕事の量」38.1% ・次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が37.5%の順に高くなっている。契約社員では「仕事の量」37.4%・「雇用の安定性」が34.6%、パートタイム労働者は「仕事の失敗、責任の発生等」35.6%・「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」34.2%、派遣労働者では「雇用の安定性」が70.7%・次いで「仕事の質」が27.6%となっている。契約社員や派遣労働者では「雇用の安定性」の割合が高い傾向があり、特に派遣労働者では突出して最も高い。
ストレスを感じている労働者は非常に多いが、その要因や背景は、年代や就業形態などにより多様であることが分かる。
こころの健康と実働時間・睡眠時間 など
主要なストレスの一つ、仕事量の多さは、労働時間の長さとして現れる場合も少なくない。
- ● 1週間当たりの実働時間が60時間を超す人の約49%が、うつ病などの傾向・疑いがあり、疲労を翌日に持越す人も約69%に及ぶ。労働時間がこころの不調につながる背景には、長時間労働による疲労の蓄積があるとみられる。
- ● 労働者の理想の睡眠時間は「7~8時間未満」が45.4%で最も多いが、実際の睡眠時間は「5~6時間未満」が35.5%で最も多い。「2~3時間」の睡眠の労働者では、66.8%がうつ病などの傾向・疑いがあった。
実働時間の多さ、睡眠時間の少なさは、共にこころの健康と正比例して、ワーク・エンゲージメント(仕事に関するポジティブで充実した心理状態。「活力・熱意・没頭」の3つが揃っている)から遠くなっていると考えられる。 - ● 人間関係、特にパワーハラスメントもこころの健康に大きな影響を与え、2022年度に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に寄せられた相談件数は、50,840件であった。
現状と今後
企業がメンタルヘルス対策に取り組んでいる割合は、使用する労働者数50人以上の事業場では91.1%と高い一方で、使用する労働者数50人未満の事業場では、30~49人の場合で73.1%、10~29人の場合で55.7%となっており、メンタルヘルス対策への取組みが低調であることが示唆されている。厚生労働省では、働く人のこころの健康を守る取組みを含む「労働者の健康確保対策の推進」が掲げられ、2027(令和9)年までに、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上とするなどを目標としている。
企業としては、ストレスチェック制度・ハラスメント対策・勤務間インターバル制度などの導入とともに、治療と仕事の両立・仕事と家庭生活の両立などを支援し、フリーランスの就業環境の整備などに取り組むことが望まれる。
このように、就業という側面からウェルビーイングの向上を図っていくためには、働き方を労働者が主体的に選択し、円滑な異動や転換、マルチキャリアパスを可能とするための環境整備や、企業による個人の希望・特性に応じた雇用管理などを推進していくことが必要と考えられる。
関連サービス
- ▼【まとめ】メンタルヘルス研修
- ▼【まとめ】ストレスマネジメント研修
- ▼【まとめ】パワーハラスメント対策(パワハラ防止)研修
- ▼【講師派遣】メンタルヘルス研修~管理職向けラインケア編(1日間)
- ▼【動画教材】健康経営シリーズ 睡眠の質を改善する習慣とマインドづくり(前後編)
- ▼【コラム】ハラスメント対策・防止の3つの視点~職場の事例から考える
最新ニュース
人事のお役立ちコンテンツ
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
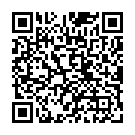
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
人事のお役立ちニュース