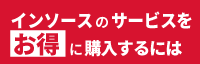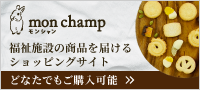《第2話》過酷なクレーム対応~対応可否の判断軸を明確にもって傾聴する
![]()
インソース講師・森義隆氏インタビュー【2】

《第2話》過酷なクレーム対応~対応可否の判断軸を明確にもって傾聴する ―
- 目次
クレーム対応のコツは「NO」のラインを明確にもったうえでの傾聴
―――それから損害保険の会社に移られて、サービスセンターの所長という、また過酷なお仕事に就かれるわけですが...。
損害保険の会社では、交通事故の示談処理とか、暴力団対策とかを担当しました。その時の経験が、現在インソースでクレーム対応研修に登壇する際のベースとなっています(笑)。
暴力団関係や、保険金詐欺などの事案を警視庁と協力して取り組むなど、サービスセンター長時代は、本当に重篤な事案ばかりを担当しました。
―――本当に大変なものだけが森さんのところに回ってくるということですね。
講義などでもお話ししているのですが、暴力団関係者よりも大変なのは一般の方が激怒されたときです。例えば、死亡事案で、初七日とか四十九日とかは、保険の交渉をするのは本当はタブーなんですが、マニュアルには事故がおきたらすぐ対応をしろと書いてある。
すると、若いうちはそのあたりの常識がないのですぐに対応をしてしまい、遺族から怒られてしまう。それを一度引き上げて、慎重に対応して傾聴して、言葉は悪いんですけどなだめて、元に戻して話をする。そういう仕事が多かったです。
生命保険会社の場合だと、クレームは始めの保険契約の段階で発生しますが、契約後はあまり問題は起こりません。しかし、損害保険は賠償という形で保険が機能するので、契約後、事故などが起こってしまってからクレームが発生します。そしてそのクレームの対応が非常に難しいのは、保険会社が対応するのが契約者ではなく、被害者だからです。
被害者にとって、保険会社のお客様である契約者は加害者にあたります。ですから、始めから被害者の方は強い怒りを持って我々保険会社の人間に接することになります。最初からクレームが起こっている状態で対応するわけです。
しかも、その怒りはそうそう収まるものではありません。特に怪我を負ったなど、体の損害に関するクレームは、非常に大きなものになります。怒りが大きいと、被害者の方は、我々保険会社の人間に「体を元の状態に戻してくれ」とおっしゃいます。しかし我々にできることは、賠償金を支払うことです。
そういったところをなんとか理解してもらうところから、対応は始まります。その後も、治療費以外に家族を養う生活費はどうするのかなど、クレームはとどまるところを知りません。
しかし、法律によりご要望にお応えできる範囲は限られています。基本的にクレームは傾聴が大切なのですが、自分たちのできることに限界があるならば、どのラインで「NO」と言うか、その明確な基準を持たなくてはなりません。
人生の転機~会社員から社会保険労務士へ
―――それから労務管理のお仕事を始められたわけですが、そのお仕事に移られたきっかけはどのようなことですか?
自分自身の性格がサラリーマンに向いていないと思ったからです。もう一つは、勤めていた会社に外資が入ってきたということもきっかけですね。そうやって独立を考えたんですが、まず同期が不動産鑑定士をやっていて、試験内容をみてもいけそうな気がしたのですが、全然それまでの経験が活かせないのでやめました。
また、税理士や司法書士も考えましたが、やはり経験が活かせません。そして、少しでも自分の経験が活かせるのは何かと考え、社会保険労務士だとわかったんです。
仕事の詳細はあまり知りませんでしたが、名前に「保険」という文字がついているので、これまでの仕事と似たところがあるんじゃないかという思い込みで飛び込みました。ですが、この思い込みはあながち的外れではありませんでした。
社労士というと、一般的には書類の代行をイメージされると思います。しかし、実際にお客様先で出てくる相談というのは、社員とのトラブルであるとか、お客さまとのトラブルであるとか、労働問題の枠に収まらない法律知識を超えた問題が多いんです。
けれど、社労士の多くは、総務や人事ご担当出身者で、そのような問題にはあまり強くない。私には営業やクレームの現場で、第一線で指揮した経験がありますから、稀少な存在として、顧客先で重宝がられました。
―――保険会社でご経験されたことが活きていますね。
そのまんまですね。たまたま資格を取ったので名刺にもつけていますけど、普段やっていることは、保険会社時代とほとんど変わりません(笑)。
(つづく)