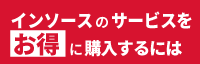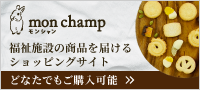自由な主義主張と論理の組み合わせが重要
![]()
すぐに実行可能なロジカル・シンキングの極意【6】

すぐに実行可能なロジカル・シンキングの極意【6】
- 目次
筆者:上林 憲雄氏(Norio Kambayashi)◇
1981年 (株)三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)入行。
英国ウォーリック大学経営大学院ドクタープログラム修了後、 2005年神戸大学大学院経営学研究科教授、経営学博士。専攻は人的資源管理、経営組織。
論理には構造がある
一般に、論理には決まった構造があります。決まった構造があるということは、"自由気まま"に自己主張をするのが論理ではない、ということを意味しています。このことを十分に理解していないと、「論理的に述べる」ことと「自由に自分の主義主張や意見を述べる」ことを同一と思い込むという過ちを犯してしまうことになります。常時、「なぜ、わたしの上司は自分の意見を聞いてくれないのだ」という不満を持っている方も居られるようですが、自分の意見を述べる前に、まず論理を組み立ててやらないといけないのです。
主義主張は、基本的に自由であり、決まった構造はありません。いわば、「好き嫌い」の世界です。好き嫌いの思いや感情だけでは相手を説得できません。
論理力と思考力とは全く別物
大学の教養の授業で「論理学」を勉強された方ならわかると思いますが、「論理」は、個人の"思い"が入り込む余地がない、無味乾燥な命題で示される世界です。
例えば、「梅干しは酸っぱい」という命題があったとすると、この「逆」の命題は「酸っぱければ梅干しである」であり、「対偶」の命題は「酸っぱくないものは梅干しではない」となります。「逆」はもとの命題と同じ意味ではないですが、「対偶」の命題はもとの命題と全く同一の意味になることが知られています。
何をつまらないことを、と思われるかも知れませんが、このように論理学の授業のようなことを敢えて述べるのは、論理には決まった構造があり、自由気ままに自己の思いを述べるのとは異なるということを示すためです。論理は、単なる主義主張とは異なり、「好き嫌い」ではなく、「正しいか正しくないか」、つまり真偽をきっちり判定できる代物です。論理を組み立て、いかに自分の「思い」が、単なる主義主張とは異なり、客観的にみて妥当であり、正当であるかを相手に示してやらないといけないのです。
論理的トレーニングに関する書物を多く執筆されている野矢茂樹氏(東京大学)は、この点を、「論理的思考力の嘘」と表現しておられます。論理力と思考力とは全く別物、ということです。
説得に必要なのは両者の組み合わせ
ただし、論理的であろうとするあまり、自由な主義主張が全く不要であるということでは決してありませんので、注意して下さい。まずは自由に発想し、その後にそれを伝える段階で論理を使えばいいのです。論理だけで説得しようとすると、むしろ逆効果になりかねません。
論理には構造があるけれども、思考の本質は自由で、相手の説得にはこの両者をうまく組み合わせてやることが肝要なのです。