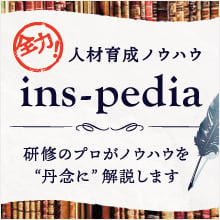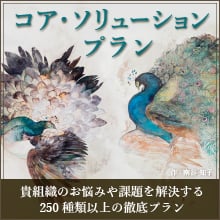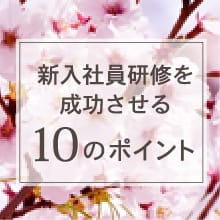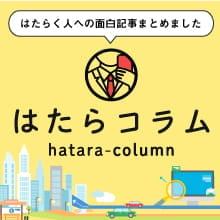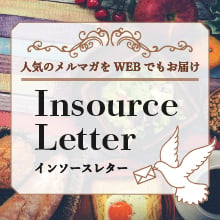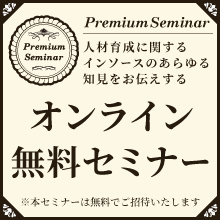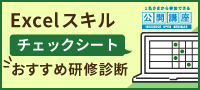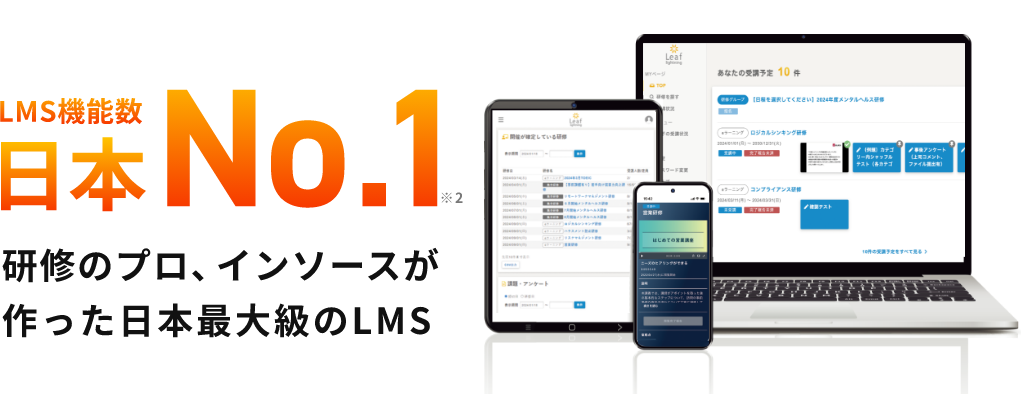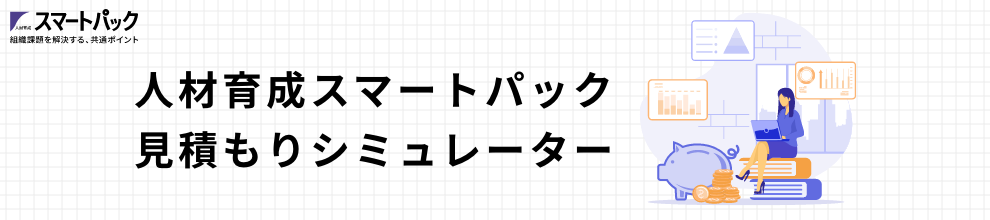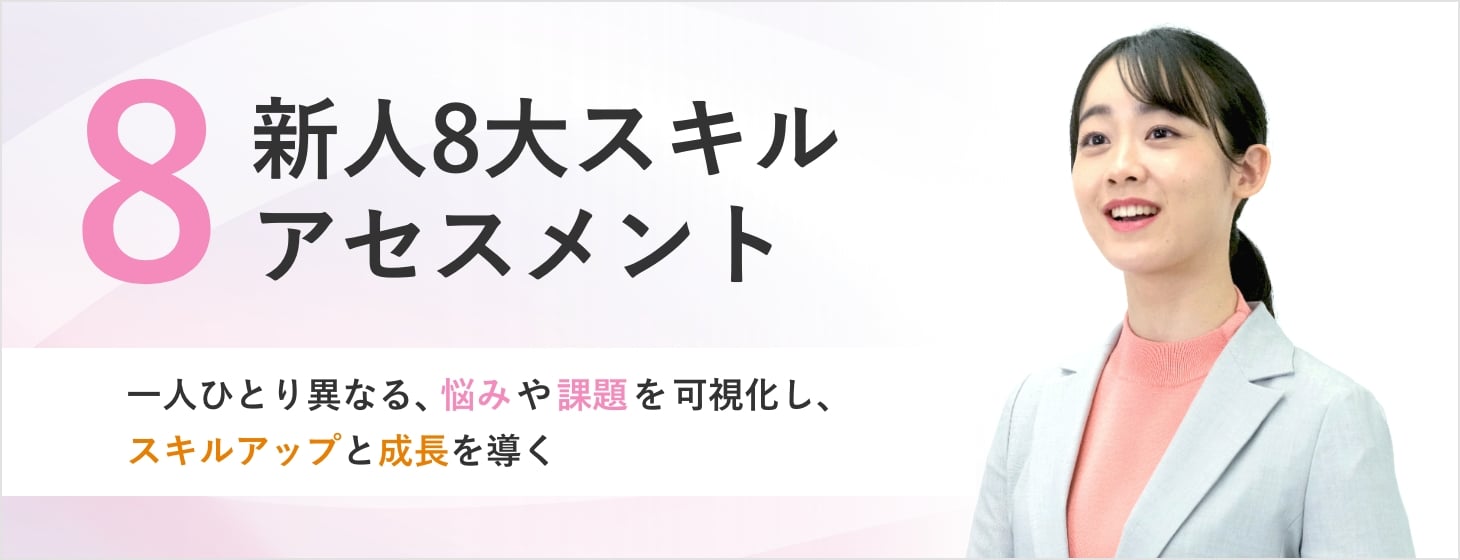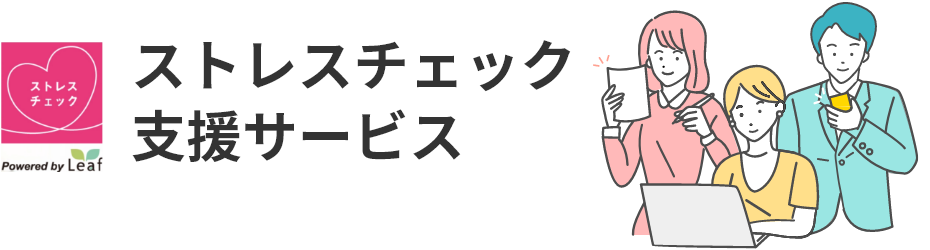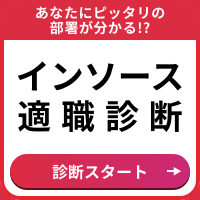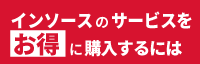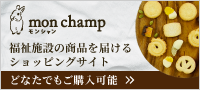2025年3月21日
失敗しないM&A、「不適切な買い手」から会社を守るには?
- <目次>
- ■ 「不適切な買い手」による被害がクローズアップ
- ■ 1. 信頼できる仲介事業者を選ぶ
- ■ 2. 買い手企業に対する徹底した調査の実施
- ■ 3. 契約内容の明確化と厳格な確認
- ■ 4. 機密情報の管理と段階的な開示
中小企業の事業承継を実現し、黒字廃業を回避する手段として普及したM&A。しかし、最近になって「不適切な買い手」が売り手の中小企業を「食い物」にする詐欺同然の事例が報道されるようになった。安全なM&Aのためには何が必要なのか?
「不適切な買い手」による被害がクローズアップ
「不適切な買い手」として大きく報道されたのが、ルシアンホールディングス。2021年からのおよそ2年間に40社近くの中小企業を買収し、売り手企業の資金を引き出し、連帯保証の解除を行わずに失踪する手口を繰り返していた。
運送会社のジョイワークでも短期間で複数の企業を買収したものの連帯保証人の変更を行わず、旧オーナーが連帯債務を負い続けるといったトラブルを引き起こしていた。
「不適切な買い手」を放置していては、中小企業の間でM&Aに対する拒否反応が広がりかねない。事業承継で中小企業の活性化を目指す経済産業省は「不適切な買い手」の排除に向け、売り手となる中小企業経営者に注意喚起する一方、仲介事業者ら関係者に対応を求めている。
警察は野放しのままだ。警視庁は2024年9月、被害者からルシアン役員2名に対する詐欺容疑の告訴状を受理したものの、現時点でも彼らが逮捕されたとの報道はない。
これはM&Aが個人相手の売買ではなく、企業間の商取引のためだ。何も知らない消費者が悪徳企業や犯罪者に騙されたわけではなく、M&Aが経営者同士の合意による商取引であることが刑事事件での立件を難しくしている。加えて株主の権限は強大だ。言葉は悪いが、全株式を取得した自分の会社を「煮て食おうが、焼いて食おうが」株主の勝手なのだ。
仮に「不適切な買い手」関係者が逮捕されて刑事上の処分を受けたとしても、彼らは吸い上げた資金を借入金の返済や個人的な遊興費などで使い果たしているケースがほとんど。加害者からの弁済は期待できない。そもそも「不適切な買い手」に十分な資金があれば、そうした詐欺的な取引などしないはずだ。
そうなれば「売り手企業」が自衛するしかない。「不適切な買い手」の魔の手を振り払うためのポイントを解説しよう。
1. 信頼できる仲介事業者を選ぶ
第三者への事業承継では、M&A仲介事業者を利用するケースが多い。その際に仲介事業者の業界内での評判や実績を確認し、信頼性の高い仲介会社を選ぶことが重要。不適切な買い手を紹介する仲介業者も存在するため、注意が必要だ。
仲介事業者を選ぶ際には、過去に「悪質な買い手」を紹介した前例がないかどうかを調べよう。「ルシアン」「ジョイワーク」「仲介」でネット検索すれば、「不適切な買い手」を紹介した事業者は分かる。ただし、大手メディアでも誤報はありうるので、報道を否定する客観的な情報がないかどうかも精査する必要があるだろう。
実際のところ、「不適切な買い手」と知りながら仲介する事業者はほとんどいない。ルシアンの場合も一度きりの仲介で、売り手企業からの苦情を受けて直ちに同社との取引を停止した事業者が多かった。1件だけの仲介実績で「信頼できない」と決めつけてしまうと、仲介の選択肢を狭めることになる。
そこで目安となるのが、M&A支援機関協会の加盟社 ※1 かどうかだ。同協会はM&A市場の健全化を図る業界団体で、経産省・中小企業庁と連携して「不適切な買い手」排除に向けた取り組みを進めている。2800件を超えるM&A支援機関のうち加盟社は134社と少ないように見えるが、M&A成約案件や従業員のシェアは60%を占める大手主導の自主規制団体だ。
※1 M&A支援機関の加盟社
https://www.maa-a.or.jp/member/
悪質な「不適切な買い手」の情報を共有する 「特定事業者リスト」に参加する60事業者 ※2 については、「不適切な買い手」を排除する上では大きな安心材料と言える。M&A仲介事業者選びの参考にしたい。
※2 「特定事業者リスト」に参加する60事業者
https://www.maa-a.or.jp/list/
2. 買い手企業に対する徹底した調査の実施
とはいえ、「不適切な買い手」を「初犯」で識別するのは難しい。買い手企業の財務状況や過去の取引実績、評判などを調査することで、詐欺的な行為を未然に防ぐことができる。特に買い手の資金調達能力や経営実態を確認することが重要だ。通常、M&A時の調査(デューデリジェンス)は売り手企業に対してのみ実施されるケースが多い。これは譲渡金額を決める上で必須だからだ。
しかし、「不適切な買い手」が現れた以上、買い手企業に対しても調査を実施すべきだろう。買い手企業から「なぜお金を出す側の会社が財務状況を明示しなくてはいけないのか」と難色を示すケースもあるかもしれない。そうした場合は仲介事業者を通じて情報開示を求めよう。それを渋るような仲介事業者ならば、交渉を打ち切る方が無難だ。
3. 契約内容の明確化と厳格な確認
契約書の条項を詳細に確認し、不明瞭な点や曖昧な条件がないかをチェックしよう。専門家の助言を得ながら売り手に不利な条件が含まれていないかを確認し、必要に応じて修正を求めるべきだ。例えば連帯保証人の変更が「努力義務」や「速やかに変更する」という曖昧な契約だった場合、法的な拘束力が弱く「契約違反だ」との主張も通らない可能性がある。
弁護士に相談するか、信頼できる仲介事業者に契約内容を確認してもらおう。被害者になったとしても経営者の責任は重い。契約に「落とし穴」がないかを見分けるため、自らも「不適切な買い手」の常套手段についての情報収集や学習を怠ってはいけない。最後に判断するのは弁護士でも仲介事業者でもなく、経営者自身なのだ。契約には万全を期そう。
4. 機密情報の管理と段階的な開示
「不適切な買い手」はターゲットになる売り手企業の資産状況を真っ先に知りたがる。事業を継続する気などさらさらなく、買収後の早い段階で現預金を吸い上げ、不動産などの資産を売り払い、あわよくば新たな借り入れをして踏み倒す算段だからだ。
売り手側としては取引初期段階に全ての情報を開示せず、相手の信用度に応じて情報を段階的に提供することがリスク軽減につながる。「不適切な買い手」は、できるだけ早くM&Aをまとめようとするものだ。言い換えれば「カモを探すために手っ取り早く資産を抜き取る会社を探す」のが鉄則。その手に乗らないためにも、早期の情報開示は避けたい。
空き巣は5分以内に犯行が完了できないと判断した家には盗みに入らないと言われる。「不適切な買い手」も交渉期間が長引くほどボロが出るリスクが高まる。明確な理由がないにもかかわらず情報提示を急かせれた場合は「不適切な買い手」の可能性があるので要注意だ。
こうした対策を講じることで不適切な買い手から自分の企業を守り、M&Aによる事業承継を安全に達成できるだろう。
配信元:M&A Online
関連サービス
- ▼【まとめ】事業承継マッチングサービス
- ▼【コンサル】人材アセスメント「事業承継に関する意識調査」の設計と実施サービス
- ▼【コラム】事業承継研修・サービス全力Q&A
- ▼【講師派遣】M&A入門研修~シナジー発揮、事業拡大のための会社の選び方(1日間)
- ▼【eラーニング】【M&A戦略を学ぶシリーズ】株式譲渡
- ▼【eラーニング】【M&A戦略を学ぶシリーズ】M&Aの基礎知識~市場の動向を理解する
- ▼【eラーニング】【M&A戦略を学ぶシリーズ】
ソーシングフェーズ(案件発掘)~効率的にM&Aを実現する - ▼【eラーニング】【M&A戦略を学ぶシリーズ】事業譲渡
最新ニュース
人事のお役立ちコンテンツ
![]() 下記情報を無料でGET!!
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
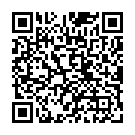
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
人事のお役立ちニュース