- クレーム対応のスキルを高めたい方
- コミュニケーションに苦手意識のある方
クレーム対応研修~臨機応変なコミュニケーションでリスクを低減する

No. 5001001 9910023
対象者
- 若手層
- 中堅層
- リーダー層
- 管理職層
よくあるお悩み・ニーズ
- クレーム対応時に、何を話せばよいか分からなくなることがある
- 伝えたいことを簡潔に相手に伝えることが苦手
- お客さまの気分を害さず、スムーズにコミュニケーションを取りたい
研修内容・特徴outline・feature
組織戦略として応対品質向上に取り組む組織が増え、サービスレベルの差が広がることにより、相対的に意識の低い組織の問題が目につくようになっています。クレーム対応において、顧客の期待水準を下回っている状態でさらに不適切な対応を行うと、顧客離反や問題の泥沼化、SNSでの拡散によるブランド毀損に繋がります。クレーム対応スキル向上はリスクマネジメントの一環であり、接客・接遇スキルと同様に組織として取り組むことが望まれます。
本研修では、クレーム対応の準備に焦点を当てて、プレッシャーを感じてしまいがちな厳しい場面を想定してスムーズにお客さまの意向や要望を汲んだ対応ができるようになることを目指します。
到達目標goal
- ①人と人とのふれあいを考慮して、当意即妙なコミュニケーションがとれる
- ②お客さまの前提知識に合わせて分かりやすく説明できる
- ③トークスクリプトの基本を学び、クレーム対応のポイントを流れで押さえられる
研修プログラムprogram
| 内容 | 手法 | |
|
講義 ワーク |
|
|
講義 ワーク |
|
|
講義 ワーク |
|
|
講義 ワーク |
|
|
ワーク |
|
7794
企画者コメントcomment
コミュニケーションは本来答えのないものです。特にクレームを申し立てるお客さまは感情的になっていることも多いため、「個」を見た対応が望まれます。しかし実際には、激怒しているお客さまを前にして頭が真っ白になったり、しどろもどろの説明で余計に怒りを買ったり、場当たり的な対応で事態を悪化させてしまうケースも多く見受けます。お客さまにとって現場担当者のイメージは組織そのもののイメージであり、クレーム対応力は組織のリスク対策のために必要不可欠なスキルです。現場担当者が自信を持ってクレームに向き合うことができるように、お客さまのお悩みや講師が抱く課題意識をもとに、「準備」に特化したクレーム対応研修を企画しました。
スケジュール・お申込み
(オンライン/セミナールーム開催)schedule・application
オンライン開催
セミナールーム開催
注意事項
- 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
- 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
- カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。
受講できそうな日時がない… 日程を増やしてほしい…
そんな時には「研修リクエスト」
「研修リクエスト」とは、お客さまのご希望の日程、内容、会場で、1名さまから インソースの公開講座を追加設定するサービスです。 サービスの詳細や、リクエスト方法はこちらをご確認ください。
※受講者数1名以上の場合から、リクエストを受け付けております
※ご連絡いただいてから研修実施まで、通常2か月程度かかります(2か月以内での急ぎの実施も、ご相談可能です)
~様々な研修の内容や選び方について詳しくご説明
よくあるご質問 ~お申込みなどの手続きや事務関連について詳しくご説明
受講者の評価evaluation
- 実施、実施対象
- 2023年3月 4名
- 業種
- インソース
- 評価
-
内容:大変理解できた・理解できた
 100%講師:大変良かった・良かった
100%講師:大変良かった・良かった 100%
100% - 参加者の声
- 相手の心情を汲み取り、マニュアル通りではない丁寧な言葉遣いや対応を心がける。組織全体の課題として、向き合う姿勢が大切だと感じた。
- 温度が高まっているお客様の対応するについて、社内で共有し活用してまいります。
似たテーマの研修recommend
関連サービスlink
読み物・コラムcolumn
インソースの「クレーム対応研修」の効果、特徴、演習(ロールプレイング)内容等について、研修制作者が語るページです。インソースのクレーム対応研修」は、お客さまにご納得いただくための「クレーム対応手順」を学ぶ研修です。座学とケーススタディで、実践力を高めていただきます。
~あなたにも簡単にできる~組織的なクレーム対応のポイントについて解説しています。一定時間対応したら「上司」や「別の担当者」に代わる、クレーム対応方法の標準化(マニュアル作成)を図る、クレーム「カルテ」を作成する、月に1回のクレーム対策会議を行うなど、自社で実践できる行動のポイントをお伝えします。
「急いで交換して!」……優先すべきは本当にスピード?クレーム対応テクニック「判断力」
単純な「問題解決」以上の対応を求められるハードクレームの場合、役に立つのが「判断軸」です。それぞれの基準の適切さや優先順位を評価(判断)して対応する力を身につけましょう。◆そもそも、「判断軸」とは何か◆お客さまの「納得度」にもとづく判断軸◆「コストとリスク」にもとづく判断軸◆「客観性の高い基準」にもとづく判断軸
お客さまからのクレームに直面し、焦りやショック、怒りなどの「つらさ」を感じたことはありませんか?事実、クレーム対応で精神的な負担をおぼえるという人は少なくありません。そんなときに少しでもラクになれるよう、心の処方箋をご用意しました。モラハラ型のクレーマーから自分の心を守る7つのポイントも必見です。
管理者は、定型通りのクレーム対応を真摯に行うことはもちろん、悪質なクレームだと感じた場合は毅然とした対応を心がけなければなりません。不当な要求を突き付けられた時、その従業員を守らなければなりません。今の時代、管理者が中心となって「モンスタークレーマー」の対応の事前準備をすることは組織にとって避けられません。組織にとっての「招かれざる客」への対応を考えます。
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、カスタマー(顧客・取引先)から受ける嫌がらせや、過度なクレームのことを指します。本ページでは、万が一カスハラにあった際の対応について、対応者本人もその上司も知っておいてほしい、法的手段の知識と対応のポイントをお伝えします。ハラスメントを未然に防ぐために今からできる準備・組織のつくり方についても取り上げます。
お問合せ・ご質問
よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明
過去にご覧いただいたページ(直近30日分)



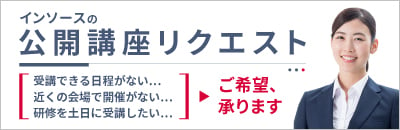

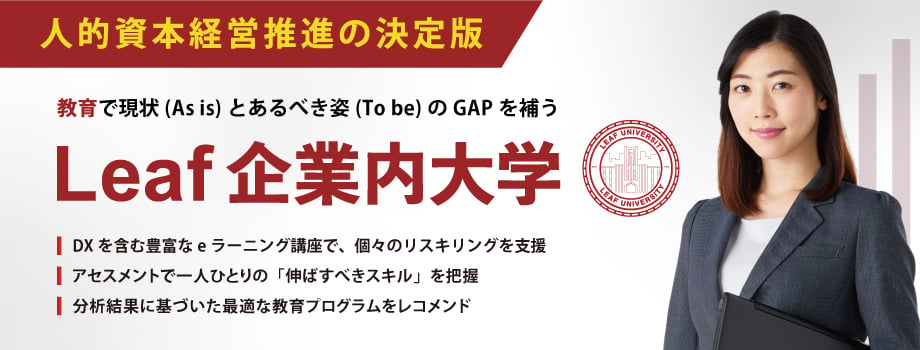



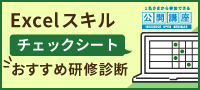


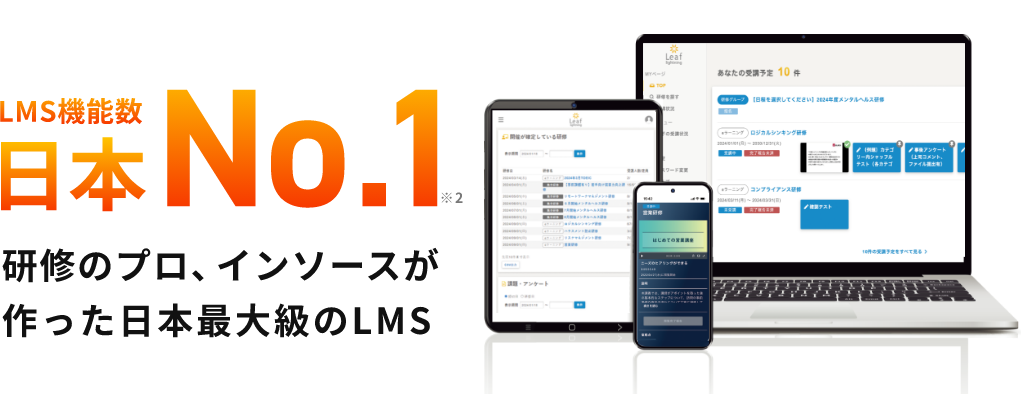



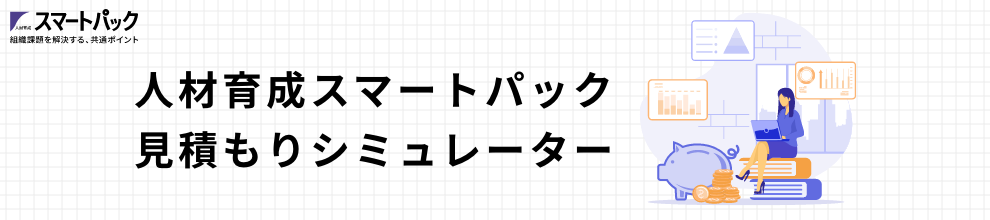
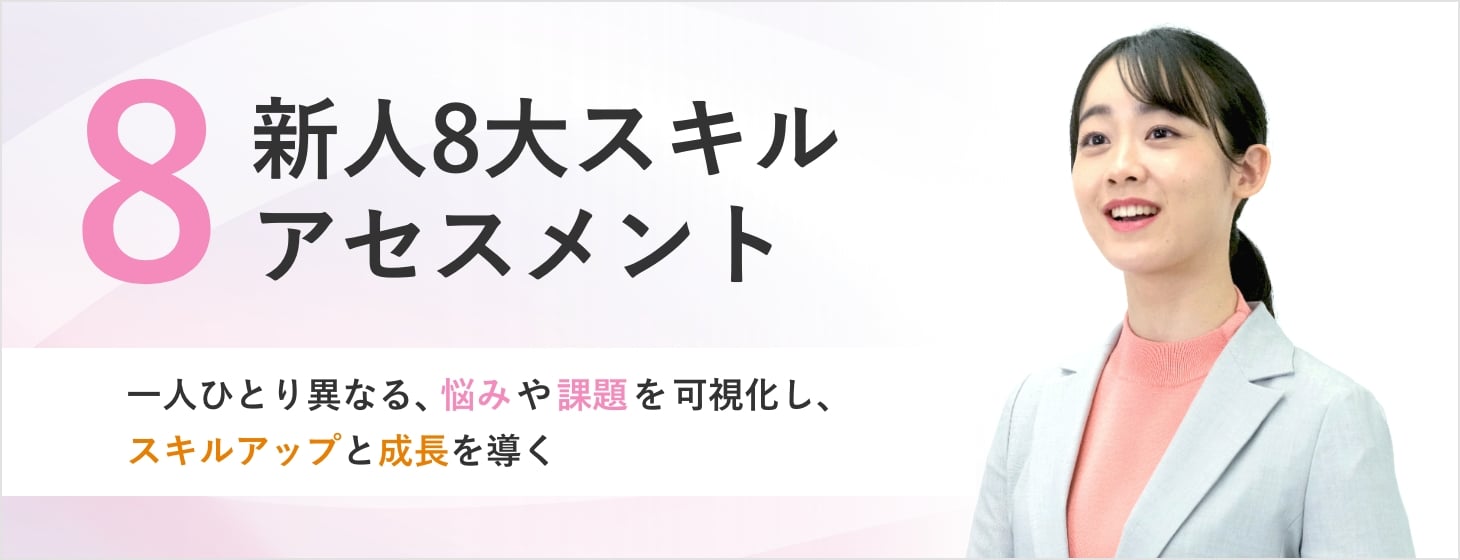





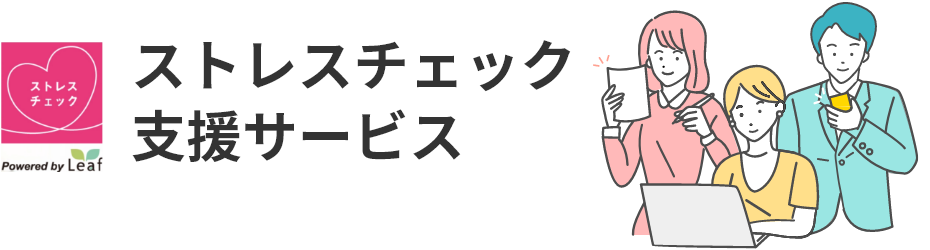




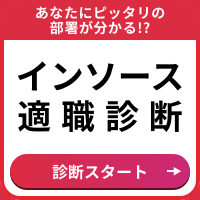


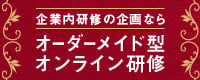
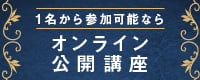


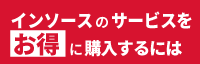

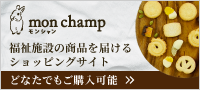
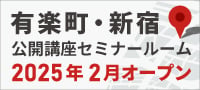


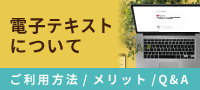


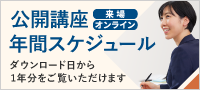



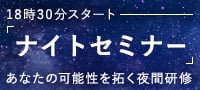
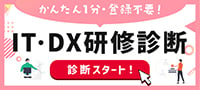





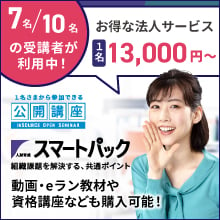




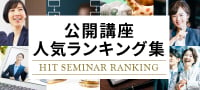
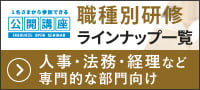

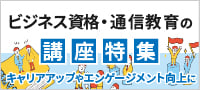
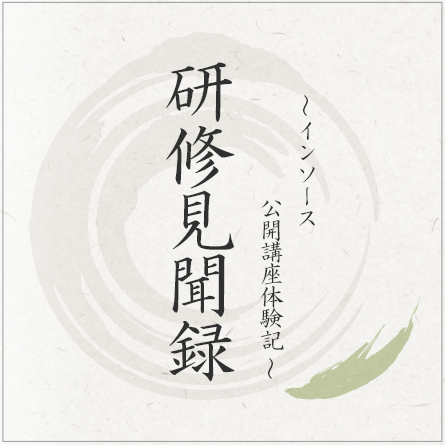







対応のバリエーションを増やし、コミュニケーションの見通しを立てることで、打てば響くクレーム対応ができる